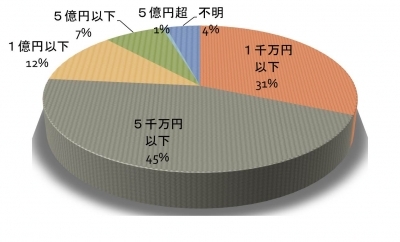「遺言信託」の費用は遺産から差し引けるか?
前回は、公正証書遺言の証人について説明しましたが、証人の役割は重く、かつ、中立であることが求められます。そのため、誰でもいいというわけにはいきません。民法974条では、以下の者は遺言の証人又は立会人となることができないと定められています(証人欠格者)。
1.未成年者
2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
1の未成年者については、遺言は15歳から可能ですが、遺言の証人は成年に達してからでないとなれません。2については、遺言者の推定相続人(遺言をする時点の相続人)や受遺者(遺言で財産をもらえる人)は、遺言の内容に強い利害関係を持ちます。また、これらの人の配偶者や直系血族も、生計を共にしていることも多く、間接的な利害関係を持ちます。そのため、遺言者が自分の自由な意思で遺言をするうえでの妨げになるので、証人にはなれません。したがって、遺言者の配偶者や子供はもちろんですが、孫や息子の嫁も証人にはなれませんので、注意が必要です。最後の3については、通常は公証人側が把握していますので、あまり問題とはなりません。
なお、公正証書遺言の証人は署名をする必要がありますので、手が不自由で署名できない人についても、事実上証人となることはできません。
上記1~3に当てはまる者が証人となって作成された公正証書遺言は、無効となります。なお、「甲不動産はAに、乙不動産はBに、それぞれ遺贈する」という内容の公正証書遺言の作成の際、証人としてBとCが立会った場合には、「乙不動産はBに遺贈する」の部分だけが無効になるのではなく、遺言全体が無効になります(したがって、Aも遺贈を受けられなくなります)。
では、上記のケースで、適法な証人としてCとDが立会って公正証書遺言が作成されましたが、その場にBも同席していた場合には、どうなるのでしょうか? つまり、適法な証人が二人以上立会っていた一方で、証人になれない者も、その現場に事実上立会っていたという場合です。
これは微妙な問題です。まず、適法な証人が二人いる以上、民法969条が定める要件は充たしているので、遺言は有効だという考え方があります。一方で、民法974条で推定相続人や受遺者が「証人又は立会人」になれないとしている理由は、これらの利害関係者がいると、遺言者が自由な意思で遺言をするうえでは「邪魔」になるためであり、Bがその場に事実上立会っていた場合でも、そのような状況でなされた遺言は無効だという考え方もあります。
この点、判例では、公正証書遺言の作成に当たり当該遺言の証人となることができない者が同席していたとしても、この者によって遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情のない限り、その遺言が無効となるものではないとしています。
この判例については批判も多いのですが、無効にならない理由として、適法な証人が二人いれば、遺言者が人違いでないこと、遺言者が正常な精神状態のもと自らの意思で遺言をしたこと、公証人による筆記が正確であることなどを確認することが可能なことをあげています。
また、法律上の立会人と事実上の立会人とでは、不正行為が行われる危険性に大きな差があり、事実上の立会人が何らかの不正を意図していたとしても、適法な証人二人がいることで、そのような不正を防ぐ効果があるというのも、その理由です。
さらに、この民法974条の証人又は立会人の制限は、公正証書遺言以外で証人を必要とする遺言にも適用されます。その中には「死亡危急時遺言」といって、病気やケガで死が目前に迫っている人が遺言をする場合も含まれます。このような場合にまで、推定相続人が事実上も立会ってはならないとすると、遺言者は今にも息を引き取りそうなのに、「今から遺言をするので、遺言者の奥さん(旦那さん)や息子さん、娘さんは、病室から全員出て行って下さい」ということになってしまい、非現実的です。
とはいえ、やはり遺言は遺言者の自由な意思に基づいて行うべきですから、そういった緊急事態でない場合には、やはり推定相続人など利害関係のある人はその場から退席してもらって、行う方が望ましいとは思います。