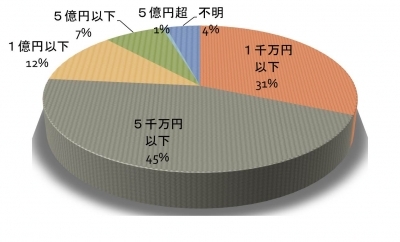遺言の文言で、「相続させる」と「遺贈する」では大違い?
遺言をするには、ある程度の判断能力(遺言能力)が必要となります。民法961条は「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定めています。なぜ「15歳」なのかというと、もともとは、明治時代に作られた昔の民法では、婚姻適齢が男性は17歳、女性は15歳であったことから、その低い方に合わせたとされています。
晩婚化の進んだ現代の感覚では、17歳や15歳で結婚というと早すぎるようですが、江戸時代以前では、男性なら元服して髪型、服装や名前を変え、女性なら日本髪の髪形を変え、お歯黒を付け、眉を引き、それぞれ大人として扱われる年齢でした。そこで、明治時代に制定された民法でも、この年齢を婚姻適齢としていたわけです。そして、17歳や15歳で結婚できると定めた以上、実際に結婚をして家庭を構えている未成年者も当然存在するので、状況により遺言をしなければならないこともありうるというのが、その理由です。なお、戦後の民法では、婚姻適齢は男性が18歳、女性が16歳に引き上げられましたが、遺言能力については15歳のまま引き継がれています。
ところで、未成年者が自動車の売買やアパートの賃貸などの法律行為をする場合には、その法定代理人の同意を得なければならないとされています。そして、民法では20歳をもって、成年としています。つまり、売買契約や賃貸契約などの法律行為を単独で行うには、原則として20歳以上であることが必要であるのに対し、遺言は15歳以上であれば可能となっています。その理由としては、未成年者が遺言を作成する場合は、法定代理人といえども代理して行うことができないこと、遺言の効力は遺言者の死後に発生するので、未成年者の財産を保護するための制度(制限行為能力者制度)をそのまま適用する必要がないこと、遺言による財産処分では、第三者の利益を害するおそれがないことがあります。
同じように、成年被後見人や被保佐人、被補助人についても、本人が単独で遺言の作成を行うことができ、代理人による遺言の作成は認められません。ただし、物事を理解する能力(意思能力)は必要ですので、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時に遺言をする場合には、それを証明するために医師2人以上の立ち会いがなければなりません。
このように、遺言の作成については、法律行為を単独で行う能力(行為能力)は要求されてはいませんが、物事を理解する能力(意思能力)は必要とされております。そのため、例えば認知症の方が意思能力のない状態で遺言をしても、それは無効となります。
実際には、遺言をした時の能力の有無を巡って、裁判になることもしばしばあります。判例では、遺言能力の有無は、「遺言の内容、遺言者の年齢、病状を含む心身の状況及び健康状態とその推移、発病時と遺言時との時間的関係、遺言時と死亡時との時間的間隔、遺言時とその前後の言動及び精神状態、日頃の遺言についての意向、遺言者と受遺者との関係、前の遺言の有無、前の遺言を変更する動機・事情の有無等、遺言者の状況を総合的にみて、遺言の時点で遺言の内容を判断する能力があったか否かによって判定すべきである」とされています。
したがって、例えば遺言が「全財産を妻に相続させる」的なシンプルな内容である場合と、複雑な内容である場合とでは、遺言者に求められる判断能力のレベルも異なってきます。判例では、「遺言者の意識状態はかなり低下し、思考力や判断力を著しく障害された状態にあったと認められる場合に、本件遺言の内容がかなり詳細で多岐にわたることを併せ考えれば、遺言者がその意味・内容を理解・判断するに足るだけの意識状態を有していたとは到底考えがたい」として、公正証書遺言でありながら無効とされた例もあります。
ところで、弁護士や行政書士が遺言の文案作成の依頼を受けることは、よくあることですが、我々法律家は、得てして複雑な文案を作成しがちになります。確かに、依頼人から報酬を得ている以上、あまりシンプルな文案は作成しにくいのも事実です。しかし、遺言者の真意を文案に反映させることは当然ですが、判断能力についても考慮して文案を作成しないと、上記の判例の様に遺言自体が無効になりかねないので、注意が必要です。もっとも、遺言は判断能力が衰える前に、きちんと準備しておくことが望ましいのは言うまでもありませんが。