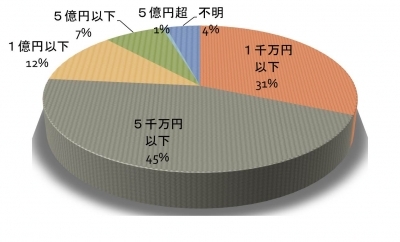遺された母の面倒をみるなら遺産を与えるという遺言は有効か?
妻と2人の息子がいる男性Xが「自宅は妻Yに、株式は長男Aに、預貯金は二男Bに、それぞれ相続させる」という内容の遺言を作成していた場合には、Xが亡くなると、遺産は原則としてその遺言の内容の通りに相続されます。
ただし、Xが亡くなる以前に妻Yが亡くなっていた場合には、遺言に書かれている「自宅は妻Yに」の部分は失効します。したがって、自宅を誰が相続するかについては、相続人全員(この場合には長男Aと二男B)で遺産分割協議を行う必要があります。
それでは、Xが上記の遺言を作成してから亡くなるまでの間にYと離婚していた場合には、どうなるのでしょうか? この場合、まずYはXの死亡時には配偶者ではないので法定相続人ではありません。したがって、自宅を元妻Yに「相続させる」ことはできません。ただし、遺言で「自宅をCに相続させる」旨が書かれていて、Cが相続人ではない場合には、登記実務上は「遺贈」を原因として、Cを所有者とする自宅の名義変更(登記)を行うことができます。その意味では、上記の例で自宅を元妻Yに「遺贈」することも、一見できそうに思えます。
しかし、問題は、それがXの意思に適っているのかどうかです。つまり、遺言を作成した時点では夫婦円満だったので「自宅は妻に相続させる」と書いたものの、その後夫婦関係が悪化して離婚に至った場合にまで、自宅を元妻Yに「遺贈」することを、果たしてXが望んでいたのかということです。
常識的に考えれば「そんなはずないだろ」となります。しかし、このような事例が裁判所に持ち込まれた場合には、裁判官としては、この遺言が撤回されたかどうかを法律的に判断する必要があります。そこで登場するのが、前回で解説した民法1023条2項の「前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する」という条文です。この条文の中にある「生前処分その他の法律行為」に、離婚や離縁などの「身分行為」が含まれるかどうかです。
判例では、「離婚」ではなく「離縁」の事例ですが、遺言者Xが養子D・Eに対し遺贈をした後に養子縁組を解消した事案において、「終生扶養を受けることを前提としてD・Eらと養子縁組をしたうえその所有する不動産の大半をD・Eらに遺贈する旨の遺言をしたが、その後D・Eらに対し不信の念を深くして協議離縁し、法律上も事実上もD・Eらから扶養を受けないことにしたというのであるから、この協議離縁は前に遺言によりされた遺贈とは両立させない趣旨のもとにされたものというべきであり、したがって、この遺贈は後の協議離縁と抵触する」として、「身分行為」による遺言の撤回を認めています。
注意しなければならないのは、この判例では単純に「離縁=遺言の撤回」とは言っておらず、「不信の念」や「扶養を受けないことにした」など、離縁に至る事情を考慮した上で遺言が撤回されたものとみなしている点です。
したがって、離婚の場合にも「離婚=遺言の撤回」になるとは限りません。もちろん、Xが元妻Yとケンカ別れをして、離婚後に別の女性Zと再婚しているような場合には、この「離婚」や「再婚」は「遺言に抵触する行為」として遺言は撤回されたとみなすことが、Xの意思に適うと考えられます。
しかし、例えば借金が返済できない状況で、債権者による財産の差し押さえを逃れる目的で戸籍上は離婚したが、離婚後も「内縁配偶者」として生活を共にしている夫婦という場合もありえます。このような場合には、遺言がないと元妻YはXの財産を譲り受けることができませんので(※第12首を参照)、離婚後も遺言を撤回せずに自宅を元妻Yに「遺贈」することがXの意思に適うといえます(なお、このような離婚や遺贈が債権者に対する詐害行為になるかどうかの問題は、ここでは触れません)。
このように、遺言を作成した方が、離婚、離縁、再婚、復縁などの「身分行為」を行った場合には、やはり、このような遺言の解釈の問題を生じさせないためにも、あらためて遺言の内容についても書き直しなどをしておくほうが望ましいと言えます。