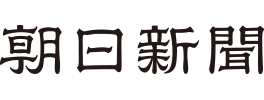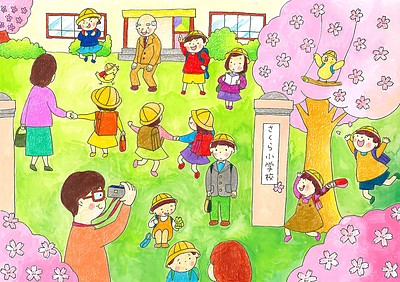特性のある子どもたちが行事に参加できるコツ(3)式の意味がまだ分からず動いてしまうお子さまの支援

前回の記事では、じっと座っていることが苦手だったり、感覚過敏があったりするお子さまが、入園式などの行事に安心して参加するためのサポートについて、「式の前・式の最中・式の後」の場面に分けてお伝えしました。
特性のある子どもたちが行事に参加できるコツ(1)
一方で、粘土やシールなど興味を引くアイテムを活用し、とにかく動かないように座っていられるようにするという方法もあります。私がサポートしている幼稚園も、以前はその方法がよく用いられていたようでした。
しかし、この方法には良し悪しがあります。
【粘土やシールでその場に留める支援のメリット】
- 座っていられる成功体験にはなる
- 静かにその場にいられる手段にはなる
- 大きなトラブルや移動を防ぐことができる
【デメリット】
- 入園式という「式典」の流れからは外れてしまう(他の子との一体感が薄くなる)
- 式典そのものを理解する機会が減る
- 周りの子が「なんであの子だけ遊んでるの?」と思うことがある
- 今後も「じっとする場面=遊んでいい」になりやすい
その場にいられるだけで「◎」としてしまうと、園全体の教育方針として「式に参加する意味」や「みんなでつくる時間の意義」が薄くなってしまいがち。そして何より、子どもたちにとってもちょっと難しいことにチャレンジしてみる機会が減ってしまいます。
ですので、粘土やシールでその場に留める支援が絶対にダメというわけではありませんが、あくまでも「緊急避難的アイテム=最後の手段」として活用し、基本姿勢としては式に参加できる工夫を取り入れた方が成長の機会につながります。
式の最中、どうしても粘土が欲しくなってしまったときは、「気持ちが落ち着かないので粘土をください」とことばで伝えられるように事前に約束をしたり、引換券を渡しておくなど、メリハリをつけて渡してあげましょう。「ひまー」と言ったらすぐに出てくるといった、なんとなくの流れで緊急避難的アイテムを使わないように気を付けてください。
また、「ここまで上手に座れていてえらかったね」など、そこまでのがんばりをほめてあげて、次につなげるモチベーションを高められるよう関わりましょう。あくまでも緊急避難的アイテムですから、徐々にその活用頻度を下げていくことが大切です。
すべてのお子さまが、「ただその場にいる」のではなく、一人ひとりが「自分も式を作っている一員だ!」と思える支援ができれば、とっても素晴らしい行事がつくれると思います。意味のある参加を大切にしつつ、先生たちのサポートでできる限り子どもたちが「式に参加する経験」を素敵に重ねていけると良いですね。