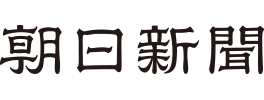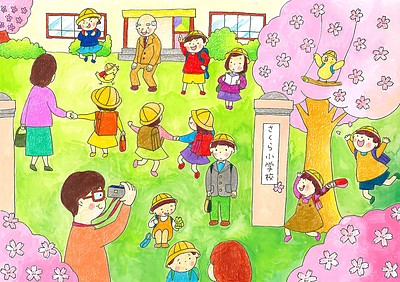発達相談はなぜ「社会福祉士(ソーシャルワーカー)」にするといいの?

私には子育てをするうえでとても大切にしている本があります。
児童精神科医である佐々木正美先生の著書『子どもへのまなざし(全3巻シリーズ)』。信頼する心理士さんから「良い本ですよ、私もいつも大切にしています」と教えていただいたことがきっかけで、出会うことができた本です。
佐々木先生は、児童精神科医として長年臨床に携わり、苦悩するたくさんの子どもたちとそのご両親の診療や相談援助を続けてこられました。
また、子どもや家族を取り巻く問題について数多くの勉強会を重ね、保育園や幼稚園など現場で働く先生たちとの意見交換を大切にされていらっしゃいました。
その体験を通して、佐々木先生は「健全で幸せな子どもを育てるにはどうしたらよいか」ということを伝え続けてこられたのです。
エリクソンのライフサイクル・モデル
佐々木先生はコロンビア大学に留学していた頃、指導教官のお一人であったクライン教授(LDの専門家)からエリクソンのライフサイクル・モデルを学びました。
エリクソンのライフサイクル・モデルとは、「人間が一生涯、健康に幸福に生きていくためには、こういう手順を踏んでいくといいですよ」というもので、乳児期から老年期まで、どういうことに気をつけて、どういう課題を達成していくべきかを示したものです。そして、それには確実に順序があり、「発達に飛び級はない」という言葉をしばしば使われたそうです。
長い臨床の仕事を続けてこられた中で、佐々木先生は、エリクソンの言っていたことが「本当にそうだなぁ」としみじみ分かるようになったと言います。
そして、現代の日本の子どもたちを見ながら、子どもたちの健全な成長のために、エリクソンの理論をどのように応用して考えればよいのか、佐々木先生ご自身も考え続け、伝え続けてこられました。
【乳児期】最初の発達課題-お母さんを信じる
エリクソンは、乳児期、幼児期、児童期、学童期、思春期・青年期、若い成人期、壮年期、老年期までの人間のライフサイクルの各段階で、こういうことさえきちんと満たしていれば、人間はほぼ間違いなく精神的に健康に、社会的にも成熟のプロセスを歩むことができるという課題を提示しました。
今回はその中で、人生の最初となる乳児期の発達課題について考えてみたいと思います。
乳児期の発達課題は「基本的信頼」。人を信じる力、つまりはお母さんを信じる力のことです。乳児期にお母さんを豊かに信じることができれば、他の人も信じることができるようになり、それが自分を信じて生きていけることにつながります。自分を信じることとは希望そのものだと、エリクソンは表現しました。
そして「基本的信頼」を育てるためには、次の姿勢が大切だと言います。
子どもが望んだように愛されること
自分では何もできない赤ちゃんは、おっぱいがほしい、おむつがぬれて気持ち悪い、寂しい、遊んでほしい、様々な要求を泣いて伝えます。そのときに、お母さんが来てすぐにおっぱいがもらえたり、あやしてくれたり、だっこをしてくれることは、赤ちゃんからすれば自分の望んだことを望んだとおりにやってもらえたということ、つまりは望んだように愛されたということになります。そして、望んだとおりにしてくれる人を信頼することにつながります。
人を信頼することができるようになってはじめて、その相手と共感する感情が育ちます。共感性により、相手に対する思いやりや喜びを分かち合う感情が育ち、大きくなるにつれて、悲しみや苦しみを思いやる感情へと発達していきます。
本当に基本的なことですが、自分の子育て経験を振り返ってみても、果たしてきちんとできたかどうか自信がありません。
佐々木先生は著書の中で次のように書かれています。
現代の親は愛し方がとても下手になりました。子どもが望んでいるような愛し方をちゃんとできる親は、本当に少なくなりました。親のほうが、自分の望んでいることを子どもに押しつけようとします。たとえば、夜泣きをしない赤ちゃんになってほしい、離乳食をちゃんと食べてほしい、おむつを汚さない赤ちゃんになってほしいなど、自分の望んでいるような子どもになってほしいという感情がとても強いのです。このような感情がとても強いと、ときには虐待までいたってしまうこともあります。
『完・子どもへのまなざし』p92-p93,佐々木正美著(福音館書店)
子どもが望んでいるような親になってあげたいと思う気持ちよりも、親が望んでいるような子どもであってほしいと思う気持ちの方が強かったのではないか、そして今もそうなのではないかと、佐々木先生の著書を読んで自問自答することばかりでした。
今からでも大切にしておくべきこと
本来、親が育児する喜びというのは、二つの観点があると思うのです。ひとつは子どもに期待できる喜び、もうひとつは、子どもを幸せにすることができる喜びです。このときに、できることなら、子どもを幸せにする喜びのほうを、ずっと大きくもって、子どもに期待する喜びは、小さくしてただきたいと思います。親が子どもに期待する喜びを、大きくもってしまった場合に、子どもからみると条件つきの愛情になるわけです。そして、その期待が過剰になってしまうと、子どもは愛されているという実感をなくしてしまいます。
『子どもへのまなざし』p294,佐々木正美著(福音館書店)
わが家の子どもたち4人は、もうずいぶん大きくなってしまいました。
みんな同じように子育てをしていても、自分のことがきちんとできる子もいれば、できない子もいます。自分の気持ちが伝えられる子もいれば、伝えられない子もいます。提出物が出せる子もいれば、出せない子もいます。愛情がきちんと受け止められる子もいれば、伝わりづらい子もいます。
ですから、同じように育てていても、親に全面的に受容された経験が足りていない子もいるかもしれません。
佐々木先生が危惧されていらっしゃったとおり、子どもの喜びよりも自分のやりたいことを優先させたり、「ママは疲れてるから自分でやって」などと言ってしまったことも何百万回もあると思います。
だからこそ、この本に出会えたことに感謝して、子どもを幸せにする喜びにあらためて目を向けられる親になっていかければいけないと思いました。
子どもの精神科の医者として、お母さんやお父さんにお願いしたいことは、子どもの笑顔や喜ぶ姿に、ご自身が喜べるご両親であってほしいということです。親の希望どおりのことを、子どもがしてくれることに喜びを感じるのではなく、子どもの希望にこたえられることに、幸福を感じられる親であってほしいということです。
「人間」の本当の幸福は、相手の幸せのために自分が生かされていることが、感じられるときに味わえるものです。このことは本当に本当です。自分の幸せばかり追求することによって得られる幸せなど、本当の幸福ではけっして、けっしてないのですから。
『子どもへのまなざし』p312,佐々木正美著(福音館書店)