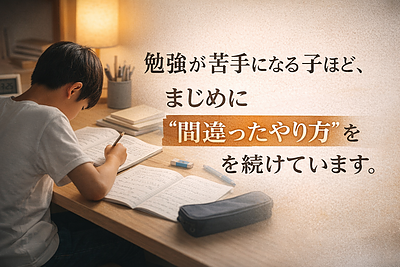「ケアレスミスが多い」という指摘で、学力は本当に伸びるのか
「分かった?」
勉強を見ているとき、保護者や指導者がつい口にする言葉です。
理解を確認する意図で使われることがほとんどでしょう。
しかし、この一言が、結果として学力の伸びを止めてしまう場面を、私は数多く見てきました。
本稿では、その理由を学習のプロセスという観点から整理してみたいと思います。
「分かった?」は理解確認の質問ではない
多くの子どもにとって、「分かった?」という問いは、理解の深さを測る質問ではありません。
実際には、
「ここで『分かった』と言えば、この場が終わるかどうか」を判断する合図として受け取られていることが多いのです。
その結果、
途中までしか理解していない
なんとなく聞いていただけ
自分で解けるかどうかは分からない
このような状態でも、「うん」と答えることが起こります。
これは怠けでもごまかしでもありません。
人間が本来持っている、「曖昧さを深掘りするより、早く終わらせたい」という心理的傾向によるものです。
「分かったつもり」が学力低下を引き起こす構造
問題は、「分かったつもり」のまま学習が進行してしまうことです。
この状態で次の問題に進むと、
解き方を思い出せない
知識がつながらない
応用ができない
といった現象が起こります。
すると子どもは、
「やったはずなのに解けない」
「説明は聞いたのに分からない」
という経験を繰り返すことになります。
この経験が積み重なると、学力の問題ではなく、自己評価の問題へと変わっていきます。
「自分は勉強が苦手だ」
という認識が形成されてしまうのです。
学力とは「理解したか」ではなく「使えるか」で決まる
学力とは、説明を聞いて理解したかどうかではありません。
理解した内容を、自力で使えるかどうかで決まります。
そのためには、学習中に以下のような思考が必要です。
記憶を自分で呼び出す
知識同士を関連づける
問題に当てはめて判断する
これらはすべて、受け身の状態では起こりません。
頭の中で情報を「動かす」時間があって初めて成立します。
「分かった?」の代わりに必要な関わり方
重要なのは、「分かったかどうか」を尋ねることではなく、分かったはずの内容を使わせることです。
具体的には、
何も見ずに説明させてみる
似た問題をその場で解かせてみる
なぜその答えになるのかを言葉にさせる
こうしたやり取りを通じて、理解が曖昧な部分は自然に表に出てきます。
これは確認ではなく、学習そのものです。
「分かった?」という言葉自体が悪いわけではありません。
ただ、その一言で学習を終わらせてしまうと、思考が止まり、成長も止まってしまいます。
本当に見るべきなのは、「分かったと答えられたか」ではなく、「分かったはずのことを、自分の力で使えているか」です。
この視点を持つだけで、子どもの学習の質は大きく変わります。
もし「分かった」と言うのに結果が出ないなら、それは努力不足ではありません。
やり方の問題です。
そのまま続けると、「自分はできない」という思い込みが固まります。
そうなる前に、学び方を変えることができます。
BesQでは“使える状態”までやり切ります。
体験で、今の理解度を一度見える化してみませんか。
学習相談 無料体験のお問い合わせは公式ラインから