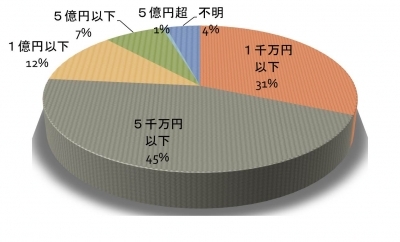遺産相続に関する書籍を上梓(出版)します!
遺言があれば、遺言者が亡くなった後、財産を相続人はもちろんそれ以外の人や法人に対しても与えることができます。また、まだ母親のお腹の中にいる胎児に財産を与えることもできます(民法965条)。このように、遺言により財産を無償で与えることを遺贈(いぞう)といいます。
遺贈により利益を受ける者を「受遺者(じゅいしゃ)」といいます。一方、遺言の内容に従って遺贈の目的となった財産を受遺者に引き渡す義務(遺贈を実行すべき義務)を負う者を「遺贈義務者(いぞうぎむしゃ)」といいます。遺贈義務者は原則として相続人ですが、遺言執行者が指定されている場合は、その遺言執行者が遺贈義務者となります。
遺贈には、「私の全財産をAに遺贈する」「私の全財産のうちの3分の1をBに遺贈する」といった具合に、遺産の全部または一定の割合分を与える包括遺贈(ほうかついぞう)と、「私の自宅の土地建物をCに遺贈する」といった具合に、遺産のうち特定の財産を与える特定遺贈(とくていいぞう)の二種類があります。
包括遺贈と特定遺贈との区別は、遺言に用いた文言、その他諸般の事情から遺言者の意思を解釈して決定すべきであるとされています。判例では、土地・建物・家財道具などをひとつひとつ特定して遺言に記載してあった場合でも、遺言をした時点での遺言者の財産がほとんど挙げられていたような事例では、これらを遺贈する行為は特定遺贈ではなく包括遺贈であるとされています。
さて、遺言者のXさんは生涯独身を貫き、人生の大半を仕事に捧げて築いた財産の全てを、自分の会社の後継者であるYさん(Xさんの相続人ではない)に遺贈するという内容の遺言をしたとします。この場合、遺言が有効であればYさんはXさんの包括遺贈の受遺者(包括受遺者)となり、Xさんの死後に、全財産を譲り受けることになります。しかし、その後の経済情勢の変化によりXさんの会社の業績が悪化し、資産が目減りする一方で負債が増え続け、Xさんが亡くなった時点では資産よりも負債の方が多い状態になってしまったとします。この場合、「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)」とされているため、YさんはXさんの資産も負債もすべて承継することになります。
このように、遺言者(遺贈者)の資産よりも負債の方が多いような場合は、包括受遺者は遺贈を放棄することができます。ところで、民法986条では、「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。」と規定されていますので、遺贈の放棄は「いつでも」できるかに見えます。ところが、この条文は特定遺贈の場合のみ適用され、包括遺贈の場合には適用はないというのが通説・判例となっています。
したがって、包括受遺者が遺贈を放棄する場合は、相続放棄の場合と同様に家庭裁判所に申述をすることにより行います。この申述は、自己のために遺贈のあったことを知った日から3ヶ月以内にしなければなりません(民法915条1項)ので、注意が必要です。なお、包括受遺者が遺贈を放棄した場合には、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属します(民法995条)。
このように、包括遺贈は相続人でない者を相続人に指定する制度に近いともいえますが、包括受遺者と相続人では以下のような違いがあります。
1.自然人だけでなく法人も含まれる。
2.遺言者の死亡以前に包括受遺者が死亡したときは、代襲相続は発生しない。
3.遺贈する財産に不動産が含まれている場合、その不動産の登記手続は、遺贈義務者と受遺者が
共同申請しなければならない。
4.包括遺贈によって取得した不動産は、登記をしなければ、その所有権を第三者に対抗することが
できない(判例)。
5.保険金の受取人が「相続人」となっていた場合、包括受遺者はこれには含まれない(判例)。
なお、資産が負債より多い場合であっても、遺言者に相続人(配偶者・子・直系尊属)がいる場合、このような遺言は相続人の遺留分を侵害することになるため、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)の対象となります。ただし、この場合でも遺贈そのものが直ちに無効になるわけではありません。しかし、紛争になる可能性もあるため、誰かに包括遺贈を行う場合には、自分の財産の状態と相続人の有無、受遺者と相続人との人間関係などについて配慮した上で遺言をしないと、受遺者にかえって迷惑をかける場合もあるので、注意が必要です。