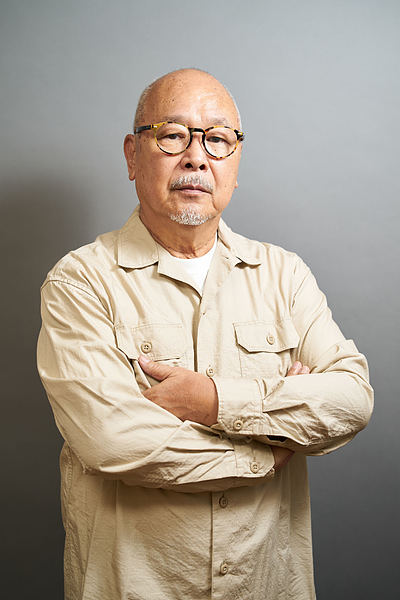小規模零細事業の経営理論:持続と適切な規模について【才藤投稿】
新型コロナウイルスのパンデミックは、私たちの生活やビジネスの在り方に多大な影響を与えました。特に、経営者としての皆さんにとって、この時期は数々の挑戦と変革の連続だったことでしょう。コロナ禍が去り、ビジネス界も徐々に元の姿へと戻りつつある中、倒産の傾向にはどのような変化が見られるのでしょうか。
業種別の倒産動向
まず注目すべきは、業種別の倒産動向です。パンデミックにより、特に影響を受けたのは観光業、飲食業、そして小売業でした。これらの業種では、多くの企業が休業や閉店を余儀なくされ、経済的に厳しい状況に追い込まれました。しかし、パンデミック後の回復期に入り、これらの業種における倒産件数は徐々に減少しています。一方で、デジタルトランスフォーメーションが加速する中、従来型のビジネスモデルに固執していた企業の倒産が増加しているのも事実です。
新たなビジネス環境への適応
コロナ禍は、多くの企業にとってデジタル化の必要性を再認識させる機会となりました。オンラインショップやリモートワークの導入など、迅速に対応できた企業は生き残り、さらには成長を遂げています。しかし、新たなビジネス環境に適応できなかった企業は厳しい状況に直面しています。特に、顧客との接触が重要なビジネスモデルを持つ企業においては、デジタル化の遅れが倒産のリスクを高めています。
資金繰りの重要性
パンデミックによる売上減少は、多くの企業の資金繰りに重大な影響を与えました。政府の支援策や融資を活用して一時的に乗り越えた企業も多いですが、支援策が終了した後の資金繰りの見通しが厳しい企業は依然として多く存在します。特に、キャッシュフローの管理が不十分な企業は、パンデミック後の回復が思わしくない場合に倒産のリスクが高まるため、注意が必要です。
ある相談の実例
コロナが終息してからは予知倒産のケースが増加したように見えます。
まだ手元に余剰資金があるため継続か倒産のどちらの選択肢もありえるというケースが以外にも多いです。
あるサービス業の依頼人のケースでは、金融機関にはリスケ手続きが終わり、1年は元金据え置きになったため毎月約120万前後の資金繰り改善、更にゼロゼロ融資の残り資金が減らず現金が貯まる現象が生じます。無条件でそうなったのではなく、経営危機がきっかけ経営改善やスリム化にも取り組んできたことが功を奏したということが前提としてあることはご理解いただきたいです。
資産を換金すると債務超過かどうかは微妙になると、そもそも倒産とは言えません。
望まない倒産が殆どですが、このケースは倒産を望んでいたがそうならないという珍しいケースかもしれません。
難しい判断としてあるのは、資金の心配は当面ないが事業自体の将来性がなく、依頼人のモチベーションがないため、中長期的には倒産のリスクが高いので早期に計画的な倒産処理をして再起するべきかどうかなのです。このケースまだ、最終的な判断の時期ではないので結論は出ていません。
経営者としての心得
経営者の皆さんにとって、この状況は一層の慎重さと柔軟な対応が求められる時期です。以下のポイントを念頭に置くことで、新たな時代のビジネスチャンスを掴むことができるでしょう。
・デジタル化の推進: ビジネスモデルの見直しとデジタル化への投資を積極的に行い、新しい市場や顧客層を開拓する。
・資金繰りの管理: キャッシュフローを綿密に管理し、余裕を持った資金計画を立てる。
・柔軟な対応: 市場の変化に迅速に対応し、変化に強い組織作りを進める。
・従業員とのコミュニケーション: 従業員との信頼関係を強化し、共に成長していく姿勢を持つ。
新型コロナウイルスの影響を受けた今だからこそ、経営者としての真価が問われる時です。未来を見据えた戦略と柔軟な対応で、新たな時代のビジネス成功を目指しましょう。


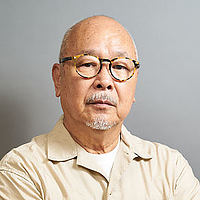
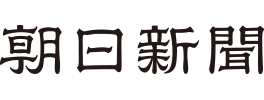


![小規模零細企業の経営者の悩み② [相談相手]経営者団体の相談担当者が頼りない](/elements/tokyo/profiles/nitemare/images/cache/image_5226171_0_75.png)
![小規模零細企業の経営者の悩み③ [相談相手]イエスマン部下しかいない](/elements/tokyo/profiles/nitemare/images/cache/image_5282896_0_75.jpg)