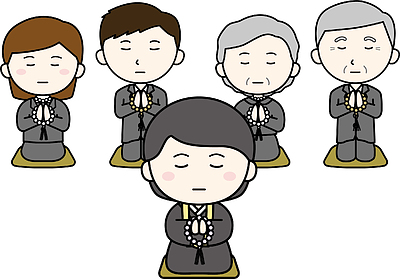「亡くなった家族の車、どうすればいい?名義変更?廃車?」
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
「親が亡くなった後、兄が『父さんから全財産を譲るという遺言書を預かっている』と言い出した…」
「でも、その遺言書が作られた時期、父はすでに重度の認知症だったはずだ!」
ご葬儀の後、このような「遺言書の有効性」を巡る、骨肉の争いが始まることがあります。
遺言書は、故人の最終意思として、本来なら相続争いを防ぐための切り札のはずです。
しかし、その遺言者が認知症であった場合、その遺言書は、かえって家族の絆をズタズタに引き裂く、最悪の“爆弾”へと変貌してしまうのです。
今回は、この極めて深刻な「認知症と遺言能力」の問題をテーマに、
- なぜ、認知症だと遺言書が無効になるのか
- 「遺言能力」があったかなかったか、それをどう証明するのか
- 実際に裁判で争われた、壮絶な立証のリアル
- すべての争いを未然に防ぐ、唯一にして最善の方法
などを、分かりやすく解説していきましょう。
【結論】遺言には「遺言能力」が必須。認知症の場合、その有効性は“作成時点の病状”で判断される。争いを避けるには、元気なうちの「公正証書遺言」が絶対
まず、法律上の大原則があります。有効な遺言書を作成するためには、その作成時点で、遺言者に「遺言能力」がなければなりません。
遺言能力とは、「遺言の内容と、それによって生じる法的な結果を、正しく理解・判断できる能力」のことです。
たとえ認知症と診断されていても、症状が軽く、作成時に遺言能力があったと認められれば、その遺言は有効です。
逆に、どんなに形式が整っていても、作成時に重度の認知症で遺言能力がなかったと判断されれば、その遺言書は法的に無効となります。
問題は、「その瞬間に、遺言能力があったかなかったか」を、後から客観的な証拠で証明(立証)することが、極めて困難であるということです。
これが、相続人間での「言った、言わない」の泥沼の争いへと発展する元凶なのですね。
このような悲劇を回避するための、唯一にして最善の策。それは、ご本人の判断能力が、誰の目にも明らかで、全く疑いのない「元気なうち」に、公証人が関与する「公正証書遺言」を作成しておくこと。
これに尽きると言えるでしょう。
1. 「遺言能力」の有無は、どうやって判断されるのか?
裁判所が、遺言作成時点の遺言能力の有無を判断する際には、一つの証拠だけでなく、様々な事情を総合的に考慮します。
裁判所が重視する判断材料:
- 医師の診断書・カルテ:これが最も重要な客観的証拠です。長谷川式スケールなどの認知症テストの点数、診断名、投薬内容、作成日当時の診察記録などが、極めて重視されます。
- 介護記録:介護認定の調査票や、介護施設の連絡帳などに記された、日常の言動の記録も、判断の助けとなります。
- 遺言内容の複雑さ:財産が多数あり、分割内容が非常に複雑な遺言は、高度な判断能力が必要とされ、無効と判断されやすくなるかもしれません。
- 遺言作成の経緯:なぜ、そのタイミングで、その内容の遺言を作成したのか。その動機が合理的であるかどうかも問われます。
- 証人や周囲の人の証言:遺言作成に立ち会った証人(公正証-書遺言の場合)や、日常的に接していた家族、ヘルパーなどの証言も参考にされます。
2. 「有効だ!」「無効だ!」泥沼の裁判で求められる“証拠の積み重ね”
遺言書の有効性を争う裁判(遺言無効確認訴訟)は、壮絶なものになりがちです。
【遺言を有効と主張する側(例:多く財産をもらう長男)の立証】:
- 「父は、日付や自分の名前はしっかり書けていた」
- 「作成当日、公証人からの質問にも、はっきりと答えていた」
- 「介護してくれた私に感謝しており、財産を遺すという動機は自然だ」
といった事実を、証拠を基に主張します。
【遺言を無効と主張する側(例:財産が少ない次男)の立証】:
- 「その時期、父はすでに私の顔も分からなくなっていた」
- 「カルテには、見当識障害が進行していたと書かれている」
- 「兄が、父をそそのかして、無理やり書かせたに違いない」
といった反論を、証拠を基に行います。
過去の記憶をたどり、親の病状というデリケートな問題を、法廷という公の場で、兄弟同士が互いに暴き合う。これは、ご家族にとって、あまりにも悲しい時間ではないでしょうか。
3. すべての争いを封じ込める「公正証書遺言+α」という最強の備え
では、このような泥沼の争いを、100%確実に防ぐにはどうすれば良いのでしょうか。
ステップ①:元気なうちに「公正証書遺言」を作成する
公証人という法律の専門家が、本人の意思と判断能力を確認した上で作成するため、自筆の遺言書とは比較にならないほど、その有効性が高く評価されます。
ステップ②:作成時に「医師の診断書」を取得しておく
これが、最強のダメ押しです。
遺言書を作成する、まさにその直前に、かかりつけ医に診察してもらい、「現時点で、遺言能力に問題なし」という内容の診断書を作成してもらい、遺言書と一緒に保管しておきます。
これにより、後から「その日は認知症がひどかったはずだ」という反論を、ほぼ完全に封じ込めることができるでしょう。
【まとめ】遺言書は“元気なうち”が鉄則。それが家族への最後の誠意
遺言書は、残される家族が争うことなく、穏やかに故人を偲ぶための「道しるべ」です。
その道しるべ自体が、疑わしいものであっては、本末転倒と言わざるを得ません。
では、本日のポイントをまとめます。
- 有効な遺言書には、作成時点での「遺言能力」が必須であり、認知症の場合、その有無が激しく争われる。
- 「遺言能力」の立証は、医師のカルテなどの客観的証拠を基に、裁判所が総合的に判断するが、極めて困難を伴う。
- 遺言書の有効性を巡る裁判は、兄弟間で親の病状を暴き合う、非常に悲しい争いになりがち。
- すべての争いを確実に防ぐには、判断能力が確かな「元気なうち」に、「公正証-書遺言」を作成することが絶対条件。
- さらに、作成時に「遺言能力に問題なし」との医師の診断書を添付しておけば、盤石の備えとなる。
ご葬儀の場で、「父の遺言書のおかげで、私たちは揉めることなく、穏やかに父を送ることができました」と、晴れやかな表情で語られるご家族がいらっしゃいます。
それは、故人となられた親御様が、ご自身の判断能力が衰える前に、家族の未来を想い、最後の責任を果たしてくださった、何よりの証拠なのですね。
その愛情深い備えこそが、残される家族にとって、最高の遺産となるのではないでしょうか。
株式会社大阪セレモニー