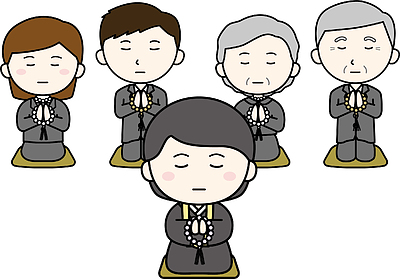メタバース葬儀はリアルを超えるか?その可能性と現実的な課題
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
「お葬式ってなんで高いのだろう…。」
多くの方が一度は疑問に思ったことがあるのではないでしょうか?
葬儀の形式や規模、そして故人や喪主様のご意向にによっては、費用は変わってきます。
また最近では、費用を抑えた小規模な家族葬や直葬(火葬式)を選ばれる方も増えています。
それでも一般的なお葬式となると、やはりまとまった金額が必要になることが多いですよね。
中には、「葬儀社は儲けすぎているんじゃないか?」なんて、厳しい声を聞くこともあります。
私たち葬儀社は、決して不当に高い料金を請求しようとしているわけではありません。
葬儀費用には、皆様が目にしている物品やサービス以外にも、様々なコストが含まれているからです。
今回は、その「費用の裏側」について、少しだけ具体的にお話ししてみたいと思います。
葬儀費用に含まれるもの
まず、基本的な葬儀費用には、どのようなものが含まれているか簡単におさらいしましょう。
葬儀本体費用: 祭壇、棺、骨壺、遺影写真、ドライアイス、式場の設営費、運営スタッフの人件費など。
車両費用: 寝台車(病院等からご遺体を搬送)、霊柩車(式場から火葬場へ搬送)、マイクロバス(参列者送迎)など。
式場使用料: 公営斎場や民間の貸しホール、寺院などの使用料。(自社ホールを持つ葬儀社の場合、プランに含まれるか別途か確認が必要です)
火葬関連費用: 火葬料金、休憩室使用料など。
飲食費: 通夜振る舞い、精進落としなどの料理、飲み物代。
返礼品費用: 会葬御礼品、香典返しなど。
これらは、葬儀の規模や内容によって金額が変動する部分です。
では、これらの費用の背景には、どのような「見えにくいコスト」があるのでしょうか?
「高い」と感じる理由の裏側①:24時間365日、いつでも対応
まず、皆さんに知っておいていただきたいのは、私たち葬儀社は**「24時間365日、いつお呼びがかかるか分からない」**仕事である、ということです。
人の死は、時と場所を選びません。
深夜であろうと、早朝であろうと、お盆やお正月であろうと、ご連絡があれば私たちはすぐに対応しなければなりません。
病院へのお迎え、ご遺体の搬送、ご安置の手配…。
これらをいつでも行えるように、常にスタッフが待機し、いつでも出動できる体制を維持する必要があります。
- 深夜・早朝の電話対応スタッフ
- 緊急搬送に対応するスタッフ(寝台車のドライバー含む)
- 夜間のご安置に対応するスタッフ
これらの人件費は、昼間の業務時間内だけでなく、24時間体制を維持するために、交代制勤務や時間外手当など、目に見えないところで常にかかっているコストなのです。
「いつでも対応してくれる」という安心感の裏には、こうした人件費が欠かせません。
「高い」と感じる理由の裏側②:専門的な設備・車両を維持管理する
葬儀には、特殊な設備や車両が必要です。
葬儀ホール(式場): 祭壇を設営し、多くの参列者を収容できるスペース。冷暖房はもちろん、音響設備や照明、遺族控室なども必要です。これらの建設費、維持費(清掃、修繕、光熱費、固定資産税など)は決して安くありません。私たち大阪セレモニーのように自社ホールを持つことは、お客様の利便性向上や費用抑制に繋がる一方、維持管理には相応のコストがかかります。
霊安室(安置施設): ご遺体を火葬まで大切にお預かりするための施設です。適切な温度管理(冷蔵設備など)、衛生管理が不可欠であり、その維持管理にも費用がかかります。
寝台車・霊柩車: これらは単なる車ではありません。ご遺体を搬送するための特殊な車両であり、車両本体価格も高価です。さらに、定期的なメンテナンス、車検、保険料、燃料費なども必要になります。特に霊柩車は、一般的な乗用車とは異なるため、維持費も割高になる傾向があります。
これらの設備や車両は、葬儀を執り行う上でなくてはならないものですが、その導入と維持には、継続的に大きなコストが発生しているのです。
「高い」と感じる理由の裏側③:専門知識・技術・経験を持つ「人」
葬儀は、単に物品を並べて流れ作業をすれば良い、というものではありません。
そこには、専門的な知識、細やかな配慮、そしてご遺族に寄り添う心が求められます。
葬祭ディレクター資格: 厚生労働省認定の技能審査制度であり、葬儀に関する幅広い知識と技能を証明するものです。資格取得のための勉強や研修、資格維持のための継続的な学習が必要です。
宗教・宗派の知識: 様々な宗教・宗派のしきたりや作法に対応できる知識が求められます。
法律・手続きの知識: 死亡届や火葬許可など、関連する法律や役所手続きに関する知識も必要です。
接遇・マナー: ご遺族や参列者に対して失礼のない、適切な言葉遣いや立ち居振る舞いが求められます。
グリーフケアの知識: 大切な方を亡くされたご遺族の心に寄り添い、サポートするための知識やスキルも重要になってきています。
これらの専門性を身につけ、質の高いサービスを提供できるスタッフを育成するためには、継続的な教育や研修への投資が不可欠です。
人件費というと、単に給料だけを考えがちですが、こうした「人財育成コスト」も、葬儀の質を維持するためには必要な費用なのです。
「高い」と感じる理由の裏側④:その他、見えにくいコスト
上記以外にも、葬儀費用には様々なコストが含まれています。
広告宣伝費: 葬儀社も企業ですから、自社のサービスを知っていただくための広告宣伝活動が必要です(ウェブサイト運営、パンフレット作成、広告掲載など)。
備品の保管・管理費: 白木祭壇や仏具など、繰り返し使用する備品の保管スペースや、メンテナンス費用。
各種保険料: 万が一の事故(車両事故や施設での事故など)に備えるための損害保険料など。
これらは、直接的に葬儀の物品やサービスとして目に見えるものではありませんが、会社を運営し、安定したサービスを提供し続けるためには必要な経費なのです。
誠実な葬儀社の努力
もちろん、「コストがかかるから、費用が高くても仕方ない」と言いたいわけではありません。
私たち誠実な葬儀社は、これらのコスト構造を踏まえつつも、いかに無駄を省き、効率化を図り、お客様に適正な価格で質の高いサービスを提供できるか、日々努力を重ねています。
例えば、私たち株式会社大阪セレモニーでは、経験豊富なスタッフが、打ち合わせから施行、アフターフォローまで一貫して担当することで、情報伝達のロスを防ぎ、効率的な運営を心がけています。
またお客様のご意向を丁寧に伺い、不要なオプションを無理にお勧めせず、本当に必要なものだけをご提案することで、無駄な費用がかからないように配慮しています。
まとめ
今回は、「葬儀費用はなぜ高いと感じるのか?」その裏側にある事情についてお話しさせていただきました。
24時間体制、専門設備、人財育成など、目に見えにくい部分にも様々なコストがかかっていることを、少しでもご理解いただけたでしょうか。
もちろん、不透明な料金設定や過剰な請求が許されるわけではありません。
大切なのは、葬儀社がこれらのコスト構造を理解した上で、企業努力によって適正な価格を設定し、その内容を包み隠さずお客様に説明すること。
皆様におかれましては、単に価格の安さだけで葬儀社を選ぶのではなく、その費用の内訳やスタッフの対応、サービスの質などを総合的に見て、信頼できる葬儀社を選んでいただきたいと思います。
後悔しない葬儀社選び! 悪徳葬儀社を見抜く7つのチェックポイ
株式会社大阪セレモニー