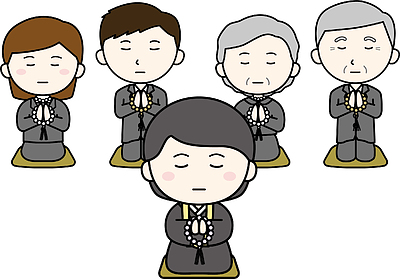「遺産分割の話し合いってどう進めるの?」
戒名のお話
お葬式の時にお坊さんから頂く”戒名”とはいったい何でしょうか?
実は戒名とは、仏の弟子になった証なのです。
本来ならば生きている間に修行をして授かるものですが、最近では仏教離れもあり、ほとんどの方が亡くなってからお葬式の時に頂きます。
『戒名』とは仏教において”受戒した者”に与えられる名前であり、仏門に入った証です。
つまり、戒律を守る印なのですね。
戒名の付け方には各宗派によって違いがあります。
真言宗では戒名の頭に大日如来を表すア号の梵字が書かれています。
浄土宗では『誉』の字が入ることが特徴で、戒名の頭に阿弥陀如来を表す梵字が入ります。
曹洞宗では経典や漢詩などを参考にしながら、対句で熟語になることが多く、戒名の頭に梵字が入ります。
浄土真宗では戒名と呼ばず”法名”と呼び、お釈迦様を表す『釋』という字が入ります。
お釈迦様のお弟子に成るという意味があるんですね。
日蓮宗では法号と呼び『日』という字がつくことが多く、男性には『法』、女性には『妙』が付くことが多いです。
自宅の仏壇にご先祖様の位牌が並んでいる場合、その家の誰かが亡くなれば、同じ宗派の戒名を授かり、ご先祖様の位牌の横に並ぶことになります。
生きていた時の名前から戒名に代わり、また仏壇に入ってしまうことによって、この世に残された私たちにとっても、「ご先祖様の一人になった」という節目の一つになるのではないでしょうか。
位牌のお話
最初に頂くお位牌は、白木の位牌です。
こちらの位牌は30センチほどの大きさで、お寺様に俗名・戒名などを書いて頂いた仮の位牌です。
こちらの位牌はお葬儀が終わると自宅に持って帰り、遺影写真・ご遺骨と共に家に飾って手を合わせる場所を作ります。
その場所を「後飾り段」といい、仏壇とは別に設置します。
こちらは、四十九日の満中陰法要が終わるまで使います。
そして、法要時までに本位牌を用意しておき、お寺様に魂入れをお願いします。
白木の位牌から本位牌に魂が移されるイメージですね。
魂を入れることによって、本位牌は故人の霊魂が宿る場所=依代(よりしろ)となり、亡くなった方の象徴になります。
四十九日法要が終わると、白木の位牌は菩提寺のお寺様にお焚き上げをお願いします。
本位牌で一般的に普及しているのは漆塗りの位牌で、他には唐木や黒檀の位牌もあります。
戒名の文字入れに二週間程かかるので、これらの位牌は前もって準備しなければなりません。
また、購入する際には大きさに注意してください。
まず、ご先祖の位牌より大きくするのは御法度で、同じ大きさかもしくは小さくします。
そして、新仏である最初の位牌を準備する際には、仏壇の上段の中央の御本尊より大きくしてはいけないのです。
位牌の台座(下の土台部分)にはデザインも沢山ありますが、これは宗派によって選ぶのではなく自由に選ぶことが出来ます。
ただ、ご先祖の位牌がある場合は、同じデザインを選ぶ方が多いようです。
原則として、浄土真宗では位牌を作るのではなく、故人の亡くなった日や生前の名前と法名を書き残す過去帳を用意しますが、浄土真宗でも高田派など地域によっては位牌を用いることもあります。
ちなみに数える単位は「柱」で、一つの時は一柱(ひとはしら)と数えるんですよ。