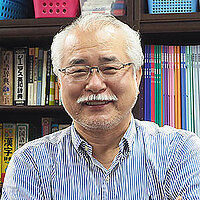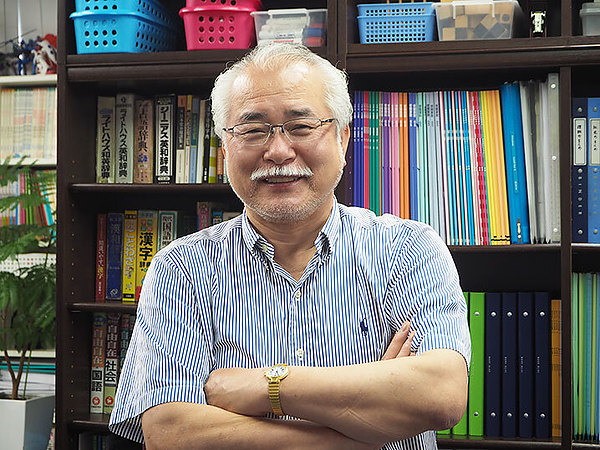折れない心
学習の意欲というものを考えた場合、高校生以上は学習の意義を自分なりに自覚して意欲を持ち続けることができるようになります。しかし、学習のいちばんの土台を形成する小中学生のころはそうではありません。この時期は学習の内容も基本的なものが多いので、学習自体はそれほど面白くはありません。また、小中学生のころは学習の意義というものを理解してそれで意欲を持つということもできません。
小中学生の意欲は、学習の意欲も遊びの意欲もすべて集団に所属したいという仲間意識から来ています。近代の学校教育が、子供たちの集団意識をうまく活用できたのは、学年別にクラスを作るという仕組みがあったからです。学年別の同質集団で、同じ学習課題に取り組むということが、クラスに対する子供たちの帰属意識を生み出していました。先生の役割は、その帰属意識を高めて子供たちの学習に対する意欲を高めることでした。
しかし、学校を取り巻く社会が文化的にも経済的にも同質である場合は、学年別クラスも同質性を保つことができましたが、やがて、社会が豊かになり、経済の格差が生まれ、社会の同質性が崩壊してくると、学校の学年別同質性に基づいた意欲づけも機能しなくなってきます。現在の学級崩壊という現象の背後には、同質性を失った社会と、そのために同質性を失った学年別クラスにおける集団意識の形成の難しさというものがあります。
欧米流の近代教育は、この解決策を社会の経済格差に合わせた同質性の回復という形で実現しました。欧米では、公立学校は貧しい家庭の学校選択の余地のない子が行くところになっています。経済的に恵まれた家庭の子供は、その恵まれた度合いに応じて私立学校に進みます。その私立学校において学年別クラスの同質性を確保し、学習に対する意欲を持続させる仕組みづくりをしているのです。日本においても、事情は同じです。戦後のみんなが等しく貧しいころは、だれもが同じ地域の公立学校に通い、同じような経済的文化的水準の子供たちが同じ一斉授業を受け、その授業の中で同質化した集団との一体感を感じて学習をしていました。
しかし、日本の社会が豊かになるにつれて、公立学校に通う子供たちは多様化していきます。小さいころから習い事に行き、学年よりも先の学習をしている子もいれば、家庭の中で読書の習慣がなくテレビやゲーム漬けになっている子もいる。そして、地域のスポーツクラブで毎日スポーツ三昧の子もいる。こういう子供たちは、小学校低学年の時点で、既に一斉授業の枠に収まらなくなります。先生の指導の工夫以前に、今、子供たちの集団の質そのものが変化し、多様化しているのです。
私立学校志向は、このような同質性の失われた豊かな社会を背景にして生まれました。ところが、そこで新たに形成された同質性は、受験を基準にしたものです。すると、その集団に対する帰属意識を子供たちの意欲に結びつけるためには、テストのランキングが最も効果的な方法になります。そのため、大人は、学習に対する意欲づけというと、すぐに競争を強化することを考えることになります。しかし、競争は単なる一つの表面的な手段にすぎません。もともと本当の子供たちの学習への意欲は、競争の勝ち負けの中にあるのではなく、集団の仲間意識の中に存在するはずです。
学校という集団で行われていることと同じことが、より目的の絞られた形で、一般的な進学塾でも行われています。進学塾における子供たちの意欲づけには、志望校に合格させるためのノウハウ、競争による刺激、先生の熱心な指導などを欠かすことができません。そして、生徒の成績が伸びると、「意欲が表出ている」、「やる気になった」と勘違いされることになります。そんな刺激で現れたやる気は、所詮、付け焼刃であり、その子の一生の財産にはなりえません。
集団で学習に取り組む場合、江戸時代の寺子屋教育では、ある意味でこの姿と正反対の教育が行われていました。つまり、寺子屋では、志望校に合格させるというような目的自体がありません。また、競争はある程度あったでしょうが、それが子供たちの大きな関心にはなってはいませんでした。更に、先生は熱心であっても過度にはならず、子供たちを遠くから見守りつつ課題を終えた子に次の課題を指示するという役割を果たしていました。もちろん、子供たちに対する一斉の授業などはありませんから、学習の内容は子供たちの思い思いの自習形式です。
このような環境で、寺子屋の子供たちは、どのようにして学習に対する意欲を持つことができたのでしょうか。現代の子供たちは、学校や塾での学年別同質集団という機能的人工的な環境で、成績の競争を刺激としてその集団に帰属意識を持って学習しています。
しかし、江戸時代の寺子屋の子供たちは、家族や地域という共同体的な環境でその共同体に帰属する意識を直接の動機として、学習に対する意欲を持っていたのです。受験や競争に勝つためという動機ではなく、家族や地域に参加するためという動機のもとに学習に対する意欲を保持していたことになります。そして、本当に学問に目覚めた者がより高次の学習環境へと巣立っていくのです。しかし、学習環境がグレードアップしても寺子屋の精神は生き続けます。それは、幕末、多く俊英を輩出した適塾でも慶應義塾でも然りなのでした。
私たちはややもすると、「意欲的な学習」、「学習への意欲」、「やる気を出す」、などの言葉のもとに、子供たちの競争意識をあおり、エキセントリックな授業を行い、徒に点数への異常なこだわりを持たせることで、集団への帰属意識の保持につなげようしがちです。しかし、学習意欲の発露は本来そのような姿形には存在せず、自分自身の内面から湧き出てくることにより本当の力となり、そのことを導き出す環境こそ真の学習環境だ、と寺子屋の在り様は私たちに教えています。