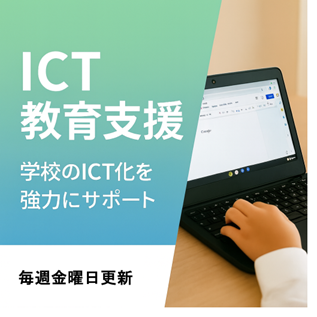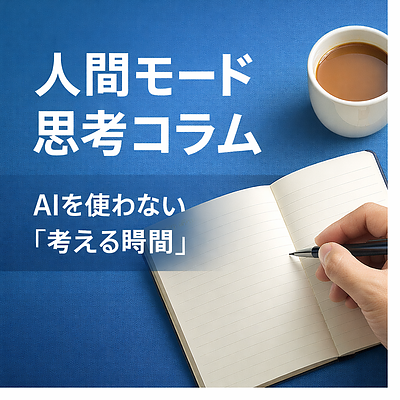ICT支援員・佐々木の現場日誌|第8回
現代の日本の教育では「競争」を嫌い、「失敗」を恐れ、平均的な昭和の教育の旧態依然とした授業が行われています。
しかし、一旦実社会へ出ると、そこは厳しい「競争」の世界です。誰も助けてはくれず、自ら考え、行動し、時には失敗を繰り返しながら成長していかなければなりません。しかし、今の教育の現場では「失敗しないこと」が重視され、子どもたちは挑戦する機会を奪われています。その結果、社会に出たときに適応できず、挫折する若者が増えているのが現状です。
とはいえ、教育の仕組みをすぐに変えることは難しいのが現実です。そのため、家庭での教育がこれまで以上に重要になってきます。学校では教えきれない「生きる力」を、保護者が意識して子どもたちに伝えていく必要があります。
1. 失敗を恐れない心を育む
社会では、挑戦なくして成長はありません。子どもたちが失敗をしたときに「なぜダメだったのか」を一緒に考え、「次にどうすればうまくいくのか?」を導いてあげることが大切です。親が「失敗=悪いこと」と決めつけるのではなく、「失敗から学ぶ」姿勢を示すことで、子どもは安心して挑戦できるようになります。
2. 自分で考え、決断する力を養う
今の子どもたちは、大人が決めたレールの上を歩かされることが多く、自分で考えて決断する機会が少なくなっています。しかし、社会に出れば自分で判断し、選択する場面ばかりです。小さなことでもいいので、日常の中で子どもに選ばせる機会を増やし、考えさせる習慣をつけましょう。「今日は何を食べる?」「どの服を着る?」「この問題はどうやったら解ける?」と問いかけるだけでも、子どもの主体性を育むことにつながります。
3. コミュニケーション能力を高める
どんなに優秀でも、人と関わる力がなければ社会では通用しません。今の時代、SNSやオンラインでのやりとりが増え、リアルな会話をする機会が減っています。そのため、家庭では親子の会話を増やし、「相手の話を聞く」「自分の考えを伝える」トレーニングを積ませることが大切です。友人や地域の人々との交流の機会を作るのも効果的です。
4. お金の知識を身につけさせる
学校では「お金の稼ぎ方」や「お金の管理」についてほとんど教えてくれません。しかし、社会に出たらお金の知識は不可欠です。子どもには、小さい頃からお小遣いの管理をさせたり、家庭内での支出について話したりすることで、お金の大切さや使い方を学ばせましょう。「どうやったらお金を増やせるのか」「お金と時間のバランスはどう考えるべきか」といったことを考えさせることも重要です。
5. テクノロジーを活用する力を養う
これからの社会では、AIやデジタル技術を使いこなす力が求められます。単にスマホやタブレットを触るだけでなく、それを「どのように活用すれば価値を生み出せるのか」を考えられる力が必要です。例えば、プログラミングの基礎を学ばせたり、生成AIを使った創造的な活動を経験させたりすることで、未来に対応できるスキルを育むことができます。
6. 自己肯定感を高める
社会に出ると、うまくいかないことがたくさんあります。そのときに「自分はダメだ」と思うのではなく、「自分にはできることがある」と前向きに考えられることが大切です。子どもの努力や成長を認め、小さな成功を積み重ねさせることで、自己肯定感を高めてあげましょう。親が「あなたは大丈夫」「挑戦していいんだよ」と声をかけることが、子どもの自信につながります。
まとめ
学校の教育がすぐに変わらないからこそ、家庭での教育がより重要になります。親として、子どもに「失敗を恐れず挑戦する力」「自分で考えて行動する力」「人と関わる力」「お金の知識」「テクノロジーを活用する力」「自己肯定感」を身につけさせることが、未来の社会を生き抜くための大きな武器となります。
私たち大人が、子どもたちに「学校では学べない本当に大切なこと」を伝え、未来へ送り出していく責任を果たしていきましょう。