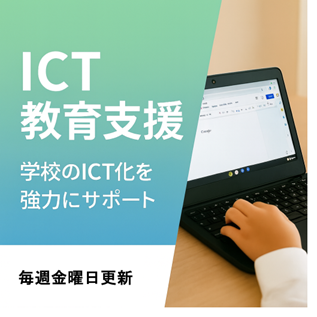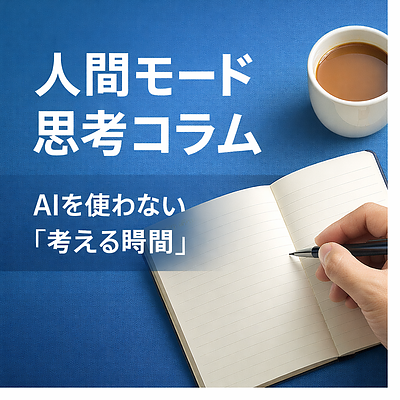久しぶりにスクラッチ!その1
私たちが日々目にするニュースやSNS、ゲームの裏側には、人工知能(AI)の技術がますます活用されています。その中でも、文章を生成したり、画像を作り出したりする「生成AI」は、未来の子どもたちの生活や学びに大きな影響を与える可能性を秘めています。
昨今、小学校や中学校で生成AIを授業に取り入れる学校が出始めており、子どもたちにとってその基礎を理解する機会が増えてきました。しかし、それと同時に、生成AIを正しく理解し、適切に活用するための「リテラシー」を育むことが必要です。特に小学生の段階からその基礎を身につけることが重要ではないでしょうか。
1. 生成AIって何?仕組みを簡単に学ぶ
まず、小学生に生成AIの仕組みを分かりやすく伝えることが大切です。「AIは人が教えたデータを元に、新しいアイデアや答えを作り出すロボットのようなもの」とイメージさせると良いでしょう。たとえば、AIが大量の本を読んで、それを元にお話を考える仕組みを例に挙げると、直感的に理解しやすくなります。
また、「コンピュータは魔法ではなく、人間が教えたことを繰り返しているだけなんだよ」と伝え、技術の背景にある「学びのプロセス」を感じてもらうことが大事です。
2. 生成AIができることとできないことを知る
生成AIの活用は無限大ですが、「万能ではない」ということも教える必要があります。以下のようなポイントを取り入れると良いでしょう。
できること:文章やイラストを作る、質問に答える、計算を手伝う。
できないこと:心を持つこと、自分で考えること、正しいか間違っているかを完全に判断すること。
たとえば、「AIが作ったお話は必ずしも本物の話ではない」「間違った答えを言うこともある」という現実を例を使って説明します。これにより、AIを盲信せず、自分で考える力を育むことができます。
3. 情報の真偽を見分ける力を育てる
生成AIを活用する際、最も重要なのは「情報を疑う目」を持つことです。生成AIが作った答えや情報がすべて正しいわけではありません。次のようなアクティビティを通じて、小学生が情報の真偽を考える力を養うことができます。
「本当かな?」と考える習慣:AIが作った情報に対して、「どうしてこう思ったんだろう?」と質問する練習をする。
情報を調べる方法を学ぶ:AIが出した答えを、図鑑やインターネットで調べ直すアクティビティを取り入れる。
4. 生成AIとの共存の大切さ
未来を生きる子どもたちにとって、生成AIは敵ではなく「一緒に考えるパートナー」となる存在です。そのため、「AIは人を助けるための道具である」という意識を育むことが必要です。たとえば、宿題や自由研究でAIを活用して効率化を図る一方で、自分の考えや工夫を加えることの大切さを教えることがポイントです。
5. 倫理と責任を学ぶ
最後に、生成AIの利用には責任が伴うことも伝えましょう。たとえば、AIが作った作品を使う場合、誰がそのアイデアを作ったのかを考えたり、不適切な使い方を避ける必要があることを教えます。
「インターネットにあるものはみんなのものではないよ」というシンプルな言葉や、「自分がされて嫌なことはAIを使ってもしない」という基本的な倫理観を養う活動を通じて、AIを正しく使う意識を育てます。
おわりに
昨今、小学校や中学校で生成AIを授業に取り入れる学校が増えている背景もあり、生成AIの基礎リテラシーを小学生の段階から学ぶことの重要性はますます高まっています。未来の子どもたちは技術に振り回されるのではなく、賢く利用し、社会に貢献する力を身につけることが求められます。
生成AIはあくまでツールの一つ。最終的にそのツールをどう使うかを決めるのは子どもたち自身です。私たち大人は、彼らが技術を使いこなす基盤を作るために、丁寧にリテラシー教育を行うことが必要です。