中古住宅の消費税はどう計算する?課税対象や税額の仕組みを解説
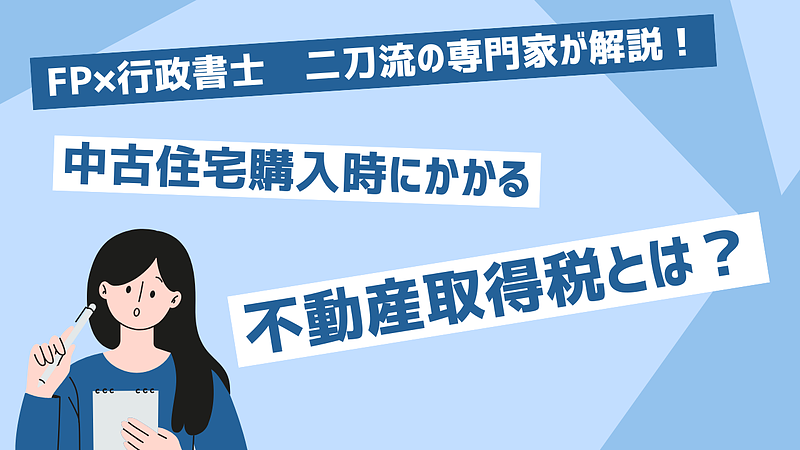
ファイナンシャルプランナー・行政書士の相澤和久です。
中古住宅を購入する際、意外と見落としがちなのが「不動産取得税」です。
物件購入の決済を終えた後、約3か月後に納付書が届きます。
不動産会社からの事前説明がないこともあり、突然の請求に驚く方も少なくありません。
不動産取得税は購入時の直接的な費用ではないため、不動産会社が案内しないケースもあります。
しかし、少なくない税額となるため事前に知っておくことが大切です。
本記事では、不動産取得税の基本や計算方法、減額制度について詳しく解説します。
目次
不動産取得税とは?誰が支払うの?
不動産取得税とは、不動産を取得した際に1回だけ課される税金です。
売買による取得の場合、購入者(買主)が支払う義務があります。
また、売買以外の取得(例:贈与)でも課税対象となります。
ただし、相続による取得は非課税です。
不動産取得税の税率と計算方法
不動産取得税の税率は以下のとおりです。
- 土地:3%
- 建物:3%(本来4%だが、軽減措置により3%)
例えば、固定資産税評価額が5,000万円の場合、税額は以下のように計算されます。
5,000万円 × 3% = 150万円
ここで注意すべき点は、不動産取得税の計算基準となるのは「売買価格」ではなく「固定資産税評価額」という点です。
売買価格とは異なることにご注意ください。
固定資産税評価額の調べ方
固定資産税評価額は、市役所や都税事務所で取得できる「評価証明書」に記載されています。
ただし、誰でも取得できるわけではなく、不動産の所有者や借地人などの利害関係者に限られます。
そのため、中古住宅購入時には、不動産会社に評価証明書を見せてもらうのが一般的です。
不動産取得税の軽減措置と適用条件
不動産取得税には、一定の要件を満たせば土地、建物それぞれ減額措置が適用される制度があります。
詳細はここでは触れませんが、主な要件は下記の通りです。
- 自分の居住用として取得(投資用は対象外)
- 昭和57年1月1日以降の建築、または新耐震基準に適合
- 床面積が50㎡以上
例えば、新築住宅の建物の場合、評価額から1,200万円が控除されます。
評価額が1,500万円なら、(1,500万円 - 1,200万円)× 3% = 9万円 となります。
実際の税額を簡単に計算する方法
不動産取得税を正確に計算するには、以下の情報が必要です。
- 固定資産税評価額(評価証明書を取得)
- 税率と計算式
- 建物の全部事項証明書(建築年)
各自治体のウェブサイトには、便利な計算ツールが提供されていますので、そちらを利用すると簡単に税額を確認できます。
ここでは私が愛用している都税事務所のサイトをご紹介します。
リンク
申請しないと減額されないケースに注意!
原則として、軽減措置が適用される場合は、自治体が自動で減額した後の税額を通知します。
しかし、「新耐震基準に適合している」ことを理由に減額を受ける場合は、自分で申請を行う必要があります。
自治体ごとに申請期限が異なり、例えば神奈川県では取得後10日以内、東京都では30日以内と定められています。
必要書類には、建築士の証明が必要なものもあるため、事前に確認して準備を進めましょう。
中古住宅の諸費用が売買価格の○%とされる理由
中古住宅を購入する際、諸費用として「売買価格の6~8%程度」と言われることがあります。
これは以下の要因によるものです。
・売買価格が基準となる費用
- 仲介手数料(約3%)
- 売買契約書の印紙代
・固定資産税評価額が基準となる費用
- 不動産取得税
- 登記費用(登録免許税)
売買価格が同じ物件でも、固定資産税評価額は物件ごとに異なるため、一律のパーセンテージで計算することができません。
そのため、「諸費用は○%程度」といった表現が使われるのです。
まとめ
中古住宅を購入する際には、不動産取得税が発生することを考慮し、計画的に資金を準備することが重要です。
また、軽減措置を活用することで、税額を大幅に抑えられる可能性があります。
事前に評価証明書を確認し、自治体の計算ツールを利用することで、正確な諸費用を把握しましょう。
不動産取得税の詳細については、各自治体の公式サイトをチェックしてみてください。
不動産取得税の申請もお任せください

マイホーム購入の不安を解消するためには、お金や住宅ローンだけはなく、不動産取引や購入する物件に対するアドバイスが必要だと考えています。
お客様のご要望にあわせて、多角的な視点で解決策をご提案いたします。
また、不動産取得税の軽減申請も、行政書士がお客様に代わって申請します。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
スマアトFP(マイホームFP相談サービス)















