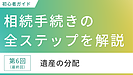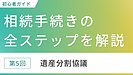【初心者ガイド】相続手続きの全ステップを解説~第6回(最終回)遺産の分配~

行政書士の相澤和久です。
本シリーズでは、実際に受任した案件をもとに、相続対策の重要性についてお伝えします。
相続手続きをスムーズに進められたケースもあれば、対策をしていなかったために相続人の負担が大きくなったケースもあります。
今回は、相続対策をしていなかったために相続手続きが困難だった事例を取り上げ、どのような対策を講じていればよかったのかを考察していきます。
事例紹介

本件は、夫(被相続人)が亡くなり、相続人は妻と2人の子ども(計3名)というケースです。
- 住まいは築40年以上の2階建て一戸建て
- 最寄り駅からバス利用でやや不便な立地
- 生活は宅配サービスを活用し、駅近くへ買い物に行くのは週1回程度
- 資産は自宅と、3つの銀行に預貯金あり
- 子どもたちは独立し、遺産について争いはなし
- 妻の口座には大きな預金がなく、夫が家計管理を担当
夫の葬儀費用を出すために銀行に相談したところ、夫の死亡が伝わった時点で口座が凍結され、引き出せなくなりました。やむを得ず、妻は自身の口座から葬儀費用を負担しました。
その後、公共料金の支払いが滞っていることが発覚。
夫の口座が凍結されたため、引き落としができなくなっていたのです。
さらに、妻は相続手続きを進めたくても、
- 何をすればよいかわからない
- 独立した子どもには相談しづらい
- 身近に頼れる人がいない
といった理由で、途方に暮れていました。
受任後の相続手続き

本件では、長男が海外在住という点が大きなポイントでした。
通常、相続人全員が国内にいる場合は比較的スムーズに進められますが、海外在住者がいると手続きに必要な書類が異なります。
必要書類
戸籍の収集
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の現在の戸籍
住民票(法定相続情報一覧図の作成)
・相続人全員の住民票(または戸籍の附票)
・海外在住の相続人の住民票は取得不可のため、在留証明書で代用可能
印鑑証明書
・相続人全員の印鑑証明書
・海外在住者は印鑑証明書が取得できないため、署名証明書(サイン証明)を使用
金融機関の相続手続き(口座解約)
- 委任状を作成し、長男にメールで送付
- 長男が印刷し、在外公館で署名証明を取得
- 署名証明が付された委任状を郵送で返送
このような手順を踏み、約1か月で解約手続きを完了し、相続人の口座に振り込まれました。
不動産の相続登記
- 海外在住の長男は、署名証明書を取得し郵送で対応
- 遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・押印を取得
- 司法書士に依頼し、妻の単独名義に変更
約1か月で登記が完了しました。
なお、相続手続きの詳細は別のコラムで詳しく解説していますのでぜひご覧ください。
相続手続きの全ステップを解説~第6回(最終回)遺産の分配~
こうすればよかった…(相続対策のポイント)

もし生前に相談を受けていたら、以下の2点をアドバイスできたでしょう。
相続手続きの負担軽減
公正証書遺言の作成
- 遺言があれば、相続手続きが簡略化される
- 遺産分割協議が不要になり、海外在住の相続人の書類手続きが不要になる
- 遺言がなければ家庭裁判所での検認手続きが必要になるため、公正証書遺言が望ましい
相続税の負担軽減(生前贈与の活用)
居住用不動産の贈与
- 婚姻20年以上の夫婦なら、居住用不動産を2,000万円まで贈与税なしで配偶者に贈与できる
- 例えば、自宅評価額が4,000万円の場合、半分を贈与することで相続税評価額を2,000万円減額可能
生命保険の非課税枠
- 生命保険金は「500万円×法定相続人の数」まで非課税
- 本件では1,500万円まで非課税扱いとなる
- 預貯金として残すよりも、生命保険として残す方が相続税負担が軽減できる
まとめ

この事例を通じて、相続対策がいかに重要かをご理解いただけたのではないでしょうか?
特に、
- 公正証書遺言の作成による相続手続きの負担軽減
- 生前贈与や生命保険の活用による相続税対策
は、相続人にとって大きなメリットとなります。
これらの対策は、元気なうちにしかできません。
「いつかは考えないといけない…」と思っている方は、ぜひ早めの準備をおすすめします。
相続手続きワンストップサービスを提供しています

煩雑で時間のかかる相続手続きを、専門家が一括で対応します。
戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書の作成、遺産の分配、すべてのプロセスをワンストップでサポートできます。
相続手続きでお困りの方、ぜひご相談ください。
初回相談は無料です。
相続手続きワンストップサービス