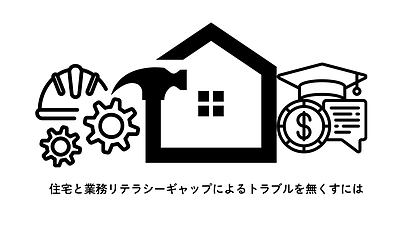家づくりで迷う人へ。まずは「自分を設計する」ことから始めよう
リテラシーギャップが引き越す住宅業界の問題
“自分ごと”の家づくりで、思わぬ落とし穴に気づけますか?
家を買う、建てる、リフォームする——
どんな選択をするにしても、住まいづくりにはたくさんの判断が求められます。
「中古を買ってリノベーションをしたい」
「土地を買って新築を建てたい」
そう思ったとき、あなたはどこまで自分で決めるべきだと思いますか?
施工会社はどう選ぶ?
見積の内容はどう読み解く?
担当者が言っていることは本当に伝わっている?
その“ズレ”が、数百万円の違いや、信頼関係の崩壊につながることもあるのです。
私たちは、“家づくりのパートナー”として、不動産の紹介だけでなく、リフォームや建築、資金計画までサポートする立場にいます。
でも実は「どこまで立ち入るべきか」はいつも迷うところです。
「お願いしてないのに、勝手に仕切られたくない」
「でも、もっと早く教えてくれればよかったのに」
—— こんな矛盾が、住まいづくりにはよく起こります。
今回ご紹介するのは、信頼し合っていたはずのプロジェクトが、
“誰も悪くないのに”うまくいかなかったある事例です。
それは、お金やスケジュールの問題ではありませんでした。
起きたのは「リテラシーのギャップ」——つまり、
“わかっているつもり”が、“伝わっていなかった”という、小さなズレの積み重ねでした。
もしこれから住まいづくりを考えているなら、
「どこまで自分で考えて、どこからプロに頼るのか」
を、ぜひこのコラムを通して考えてみてください。
あなたの家づくりが、幸せなプロジェクトになることを願って——。
「こだわり客」×「職人社長」=最強?最悪?
「いい家をつくりたい」という願いは、いつだって希望に満ちている。
このプロジェクトも、最初はその希望がキラキラと溢れていた。
物件は、中古戸建。
古くてしっかりした、いわゆる“昔ながらの大工さん”が丁寧につくった大きめの家。
骨組みの強さを活かしながら、耐震と断熱性能をしっかり上げ、心地よく、そして静かに暮らせる家にしたい――。
そんな施主の願いに共感し、リノベーションを担ったのは、設計にもセンスがあり、こだわりのある工務店の社長、Sさんだった。
初期の打ち合わせは、とても楽しそうだった。
施主のOさんは、性能や素材に対しての知識も高く、情報収集も自ら行い、ショールームも積極的に回るタイプ。
一方、Sさんは物腰が柔らかく、おっとりした語り口で、こだわりのある住まいづくりを得意としていた。
「この二人なら、いい家ができそうだな」と、わたしも思っていた。
普段の私は、家づくりを土地探しからリノベーションまで一貫してプロデュースすることが多い。
だが今回は、Oさんが「自分で仕切れる」と強く自信を持っていたこともあり、不動産購入の引き渡しまでをサポートし、その後は工務店と直接進める形をとった。
「任せてください、大丈夫です」と話すOさんの姿に、私も安心していたし、信頼もしていた。
でも──
この「自信」
が、後に厄介な問題となっていくとは、当時の私には予測できなかった。
Sさんは、誠実な人だ。
デザインや性能には確かなこだわりがあり、家づくりに真摯に向き合う“職人タイプ”。
ただ、いわゆる“段取り屋”ではない。
スケジュール管理や資料の整理、全体像を整理して進行をマネジメントするような力は、決して得意ではない。
お客様とのコミュニケーションも、丁寧な反面、ときに核心が抜け落ちるタイプだ。
それでも、Oさんは仕事でもマネジメント経験があり、住宅についても自ら学びながら丁寧に準備を進めていた。
「もしSさんが不得意な部分があっても、自分がマネージできれば問題ない」と、どこか確信めいた様子さえあった。
この「安心感」と「信頼感」こそが、最初のすれ違いだったのかもしれない。
家づくりは、相手を信じるところから始まる。
でも、その信頼は「わかり合えている」という前提があってこそ。
お互いに、「このくらいなら伝わっているだろう」「このくらいはわかってくれているだろう」と思った瞬間から、ほころびは始まる。
“通じ合っているように見えて、実は通じていなかった”
――そのギャップが、この後のすべてのトラブルの種になっていた。
「好きなことが一緒」だけでは、家づくりは成功しない。
「目指しているゴール」と「進め方に必要な段取り」が共有できていないと、いくら想いがあっても、その家は完成までたどり着けない。
]“住まいの専門家”はいても、“段取りの専門家”がいない[
家づくりがスムーズに進むかどうかは、実は“技術力”より“段取り力”
にかかっている。
このことを、OさんとSさんのプロジェクトは私たちに見事に教えてくれた。
着工が予定より遅れはじめた頃、ある打ち合わせが行われた。
内容は、防音室の仕様確認。
Oさんのこだわりのひとつであり、家づくりの大切な要素だった。
この日は、防音室の専門業者とSさんとのオンラインミーティング。
Sさんが段取りをしてくれた打ち合わせだったが、その場にいたOさんのメールには、次のように書かれていた。
・・・・・・
担当者は現場の合間を縫ってビデオ会議に参加。SさんのiPadには資料が見つからず、先方が画面を共有してくれた。
そもそも業者さんも打ち合わせの趣旨がわかっておらず、私がその場で説明。
私が事前にSさんへ送っていた防音室の仕様書も、業者へは共有されておらず、その場で私が説明する羽目に。
すべての段取りが甘い。私は業者と直接連絡が取れるからまだ救われたが、工務店が間に立つ意味がない。
「あれ、これ、私が全部やるんですか?」という気分でした。
・・・・・・
こういう話を聞くと、「たまたまうまくいかなかっただけでは?」と思う人もいるかもしれない。
でも、私は知っている。
こうした“ズレ”は、最初からずっと、いくつも小さなサインとして現れていたことを。
Sさんは施工力のある人だ。
素材を見る目もあり、図面も書ける。
だが「段取りが苦手」なのだ。
プロジェクトの全体像を俯瞰して、どの資料がどこに必要で、誰に何をいつ共有すべきか、ということに意識が及ばない。
しかも、それをサポートできるスタッフも不在だった。
たとえば、打ち合わせに必要な最新の図面。
平面図や立面図は日々変更されていくものなのに、Sさんは最新版を施主や業者に送っていなかった。
共有はメール添付のみ。図面の格納場所がなく、バージョン管理もされていない。
資料セクションに整理されておらず、Oさんは毎回「どれが最新版なのか」探しながら確認せざるを得なかった。
これでは、せっかくの打ち合わせもただの“時間泥棒”だ。
そして、それに気づいていないSさんには、当然ながら“謝罪の言葉”もない。
打ち合わせのたびに有給休暇を取り、サンプルを集め、ショールームにも足を運び、自らの時間を「自分の理想の家のために」注ぎ込んでいたOさん。
彼にとってこのプロジェクトは、“わたしごと”そのものだった。
一方で、Sさんにとっては、いくつかある仕事のうちのひとつ。
もちろん手を抜いていたわけではない。
ただ、同じ温度で向き合っていたとは言えなかった。
いや、正確に言えば、「向き合い方の種類が違った」のだ。
Sさんは、家そのものを“丁寧につくる”人だった。
Oさんは、“プロジェクト全体を丁寧に進めたい”人だった。
どちらも正しい。
でも、違っていた。
その「違い」を埋める誰かが、ここにはいなかった。
図面を整え、スケジュールを引き、資料を管理し、思いのズレを翻訳する人――
つまり、「段取りの専門家」が不在だった。
そして、建築の現場には、そういう人材が圧倒的に足りていない。
“住まいの専門家”はいても、
“段取りの専門家”がいない。
これが、今の住宅業界の深い深い盲点だ。
追加2000万がサラッと告げられた日
プロジェクトが動き出して数ヶ月。
予定通りには進んでいなかったが、Oさんはできる限り丁寧に対応していた。
平日の打ち合わせには有給を取り、資料は自身で整理し、カタログやサンプルも集め、考え抜いた要望リストは100項目以上にのぼった。
「自分の家だから、ちゃんとやりたい」
その気持ちは誰よりも強かった。
だからこそ、「任せきりにはしない」。
「自分がマネジメントすれば大丈夫だ」と思っていた。
そう、それは“信頼”というより“覚悟”だったのかもしれない。
そして、ある日――
Oさんのもとに、1通のメッセージが届いた。
そこには、こう書かれていた。
「全体でざっくり+2200万くらいになるかと思います」
それは、まるでランチの誘いでもするような、軽やかなトーンだった。
しかしOさんにとっては、青天の霹靂。
当初の予算5000万円は、融資手続きも完了し、すでに契約も済んでいる金額だった。
それが、突然7500万円に膨らんでいる。
しかも、それまでの7ヶ月間、追加費用の話は一度もされていなかった。
――なぜ、今?
――なぜ、こんなにさらっと?
――本当に、この人に任せて大丈夫なのか?
積み重なってきた小さな「違和感」が、一気に崩れた瞬間だった。
Sさんの言い分はこうだった。
「もともと入れていた太陽光や外構を引けば、そんなに増えていないと思っていた」
「追加の要望が増えたから、そのぶんだと思う」
「銀行用の見積もりには必要最低限しか入っていなかった」
Oさんは言った。
「最初の見積のときから、防音対策とセルロースファイバーはお願いしていた」
「要望リストも渡していたし、仕様の前提条件も共有していた」
「それを見積もりに反映しないまま7ヶ月進めたのは、どう考えてもおかしい」
Sさんは静かにうなずき、「すみません」とは言った。
でも、謝罪というより、「理解した」だけのように感じられた。
Oさんの内心には、こんな言葉があった。
「これはもう、仕事として成立していない」
「一式」という言葉に隠されてしまう見積。
階段や窓の収まり、細かい造作、素材のグレード――
どれを取っても、こだわれば価格が変わる。
それなのに、どこにどれだけの費用がかかるのか、説明もなく「まあ大体こんな感じです」と言われる。
「Oさんが費やした時間は、時間単価で換算すれば500万円を超えています。
でも、それを誰にも請求できないのはわかっている。
ただ、それに見合う“仕事”が返ってきていないのは、納得できない」
このプロジェクトは、“いい家”をつくることが目的だった。
けれど、Oさんにとってそれは、“信頼できるプロとともに、理想の暮らしを形にしていくこと”でもあった。
つまり、「家」だけではなく、「関係性」
も含めた“成果物”だったのだ。
だが、工務店側は「ものづくり」には向き合っていたものの、
「関係づくり」には向き合っていなかった。
このすれ違いこそが、最も大きな“見積外コスト”だった。
リテラシーギャップは、心の亀裂を生む
リテラシーギャップは、心の亀裂を生む
Oさんは仕事ができる人だった。
資料は整理され、返信は的確、指摘も冷静。
建築の専門家ではないが、施主としての情報収集は徹底していた。
それは「任せきれない」という不安の裏返しでもあり、
「自分が主導しないと進まない」という危機感でもあった。
Oさんには、ビジネスに対するリテラシーがあった。
仕事の基本=報告・連絡・相談(ホウレンソウ)
スケジュールを守ること、資料を整理すること、敬意を示すこと。
社会人として“当たり前”のことだ。
だが、Sさんにはその“当たり前”が、当たり前ではなかった。
■ メールを送っても返信がない
■ メッセージは断片的で、資料添付だけで説明がない
■ 打ち合わせの日にちも、確認をしないまま予定を入れる
■ 見積の最新版がどれか分からない
■ 要望が反映されたかどうか、図面にも仕様書にも記載がない
Oさんは一つひとつをメモし、指摘し、改善を促した。
でも返ってくるのは、“ふんわりとした受け流し”と、曖昧な言葉だった。
「あ、忘れてました」
「今週中には何とか」
「あとでまとめてお送りします」
こうしたやりとりが何度も続くうちに、Oさんは静かに怒りを募らせていった。
「これは、信頼の問題だ」
と。
問題の本質は、「建築リテラシー」ではなかった。
問題は、「仕事に対するリテラシーの差」だった。
Oさんは、建築の詳細についてはプロではなかった。
だが、コミュニケーションの段取りやマネジメントについては、プロだった。
一方、Sさんは建築のプロではあったが、「伝えること」「詰めること」「判断を仰ぐこと」については、極めて不器用だった。
この“リテラシーの非対称性”が、どちらかが悪いのではないのに、関係性を壊していく。
私は常々思っている。
家づくりにおいて最も深刻な“ミス”は、「構造計算の見落とし」でも「仕様の間違い」でもない。
それは――
「相手の前提が見えていないまま、進めてしまうこと」だ。
Sさんにとっては、「施主のこだわりに全部付き合っていたら進まない」という思いもあったのだろう。
Oさんにとっては、「自分がここまでやっているのに、どうして反応が返ってこないのか」という怒りがあった。
どちらも間違っていない。だが、通じ合っていない。
Sさんにとっては、“いつもの家づくり”のひとつだったかもしれない。
でも、Oさんにとっては、“人生の時間を賭けたプロジェクト”だった。
そこに温度差が生まれるのは、当然だ。
だが、その差を埋める存在がいないとき、
信頼は、音もなくすり減っていく。
リテラシーとは、知識のことではない。
**「相手と対話するための基盤」**である。
Oさんには、言葉を尽くして伝える力があった。
だが、受け取る相手にその土台がなければ、どれだけの誠意も、空を切る。
一方で、Sさんにも言い分はある。
「こだわりの強い施主に、すべてを合わせ続けていたら、現場が回らない」
「現場で判断すれば済むことを、すべて書面に落とす必要があるのか?」
「いつまでも仕様が決まらず、下請けに見積も出せない」
これもまた、正論だ。
でも、その“正しさ”が“通じる”とは限らない。
ましてや、通じないまま走るプロジェクトが、満足なゴールを迎えることはない。
「住まいの代理人」は、感情と現場の翻訳者である
OさんとSさんのケースを見て、あらためて思う。
このふたりの“ズレ”を最初に気づいて、言葉にできる人がいたら――
このプロジェクトは、もっと違った未来があったかもしれない。
私たちは、家づくりの“黒子”ではない。
でも、“主役”でもない。
私たちの仕事は、その間を縫い、つなぎ、翻訳することだ。
たとえばOさんのような施主は、今後ますます増えていくでしょう。
■ 年収が高く
■ ビジネスリテラシーがあり
■ 情報収集力も行動力もある
■ でも建築ははじめて
こうした人たちは、建築の知識をどんどん吸収し、
「自分で考えて、自分で決めたい」と願う。
でも、施工の現場は、別のロジックで動いている。
■ 下請けとの関係性
■ 現場監督の段取り
■ “一式”という曖昧さ
■ 職人の習慣、手配、納期、癖
ここに、“翻訳”が必要になる。
Oさんが感じていたのは、「仕事ができない」という怒りではない。
「伝えたのに伝わっていない」「期待したのに無視された」という、感情の消耗だ。
そしてその消耗が、“不信”へと育っていく。
一方、Sさんもまた、口には出さないが、疲れていたはず。
「この施主はこだわりが強いな」
「毎回の打ち合わせが長すぎる」
「どこまで求められるんだろう」
そんな思いが、無意識のうちに“後回し”や“反応の鈍さ”となって、表に現れていた。
この状態では、誰が悪いとか、正しいとかいう話ではない。
お互いの価値観のずれ、ボタンを掛け違えたまま。
お互いが修正をしようとしても修正の仕方にまたギャップがあったのではないか。
私はこう思う。
だから「住まいの代理人」が必要なのではないかと。
「住まいの代理人」とは、“家のプロ”ではなく、**“関係性のプロ”**だと。
建築士が設計をし、工務店が工事をする。
その“あいだ”に立つ第三者こそが、現場全体を俯瞰し、感情を読み、意図を翻訳し、段取りを整える。
それが「住まいの代理人」の役割だ。
Oさんのような高リテラシーの施主であっても、
「建築現場をマネジメントする」というのは、まったく別のスキルが必要になる。
知識があっても、段取りが読めない。
ロジックが通っても、相手が動かない。
そういう世界だ。
本当は、私がこのプロジェクトに最初から関わっていたら、
こう言っていただろう。
•「その見積、“一式”ではなく内訳をください」
•「この要望リストは、どこまで反映されていますか?」
•「サンプルと資料は、次回までに整理しておいてくださいね」
•「このままだと、施主が不信感を持ちますよ」
•「仕様が決まらないと、見積も出ません。段取りを逆算しましょう」
つまり、「火事になる前の小火(ぼや)を消す人」が必要だったのだ。
火がついてから騒いでも、手遅れになる。
信頼関係が崩れる前に、「そろそろ危ないですよ」と指摘できる人が必要だ。
今、住宅業界にはそういう人がいない。
設計と施工の間。
営業と顧客の間。
現場と管理の間。
その“すきま”を埋める専門家が、ほとんど存在しない。
でも、その“すきま”でこそ、トラブルの芽が育つ。
信頼のヒビが生まれる。
だから私は、「住まいの代理人」が必要だと信じている。
“わたしごと”になれなかった家づくりが教えてくれたこと
このプロジェクトは、最初から“うまくいかない家づくり”ではなかった。
むしろ、理想的な出会いだったはずだ。
Oさんは情熱と知識を持った施主。
Sさんはこだわりと技術を持った工務店の社長。
どちらも、「いい家をつくりたい」と心から願っていた。
でも、結果的に、信頼は何度も揺らぎ、
最後まで「スムーズだった」とは言えない道のりとなった。
なぜか。
理由はただひとつ。
“わたしごと”のズレだ。
家づくりを「わたしごと」として真剣に取り組んでいたのは、施主のOさんだった。
でも、工務店側にとって、それは「仕事のひとつ」でしかなかった。
決して手を抜いていたわけではない。
でも、「毎日そのことばかりを考えている人」と、「複数案件を抱えている人」の間にある温度差は、
いつか必ず亀裂を生む。
Oさんは「自分でマネジメントできる」と思っていた。
でも、建築の世界は、自分ひとりの努力ではコントロールできない。
Sさんは「施主のこだわりに応えたい」と思っていた。
でも、段取りや対話が追いつかないまま、信頼を失っていった。
こういうとき、たいてい誰かが言う。
「施主が細かすぎるんじゃないか?」
「工務店がもっとちゃんとしていれば…」
「それなら設計事務所に頼めばよかったのに」
でも、そんなことじゃない。
問題の本質は、“関係性の設計”がなかったことだ。
家の設計はしても、
関係性の設計は、誰もしていなかった。
私は思う。
これからの家づくりは、
「ものづくり」だけでなく、「関係づくり」までを支援できるプロが必要だ。
それは営業でもない。設計でもない。現場監督でもない。
施主の想いを“設計図”に変える人
プロの段取りを“翻訳”できる人
気持ちのズレを“関係性”として整える人
そんな“第三の存在”がいて初めて、
家づくりは「わたしごと」として完結するのだと思う。
Oさんのような施主は、これからもっと増える。
自分で調べ、考え、納得して選びたいと願う人。
だからこそ、家づくりを“商品購入”としてではなく、
人生のプロジェクトとして見つめる人たちが、次の時代の施主になる。
そんな人たちのそばには、
“住まいの代理人”が必要になる。
この仕事は、まだ世の中に知られていない。
でも、火事を防ぎ、信頼をつなぎ、感情を翻訳するこの仕事が、
誰かの“わたしごと”を守っている。
だから、私は声を大にして言いたい。
家づくりは、“わたしごと”になった瞬間に、動き出す。
でも、“わたしごと”であり続けるためには、支えてくれる“誰か”が必要だ。
だからこそ、
ただ事例を見て、
ただ親切にしてくれたから、
ただ契約前に感じがよかったから――
それだけで“代理人”を決めないでほしい。
その人は、
あなたの代わりに“あなたの仕事”をしてくれる人か。
あなたの想いを、“わたしごと”として引き受けてくれる人か。
本当に、そうだろうか。
家をつくるということは、人生を形にするということ。
そして、それを一緒に歩く人を選ぶということ。
家探しの始まりは、「代理人」探し。
「この人となら、きっと大丈夫」
そう思える人と出会えるまで、あきらめないで探してほしい。