年金に強い社会保険労務士
藤原武志
Mybestpro Interview
年金に強い社会保険労務士
藤原武志


#chapter1
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの藤原武志さんは、2010年、地元町田市にて藤原事務所を開設。法人向けに労働保険・社会保険手続きの代行、就業規則等の整備などの人事・労務管理、そして顧問契約を行っています。「中小企業のオーナーの方々にとって、人事や労務管理をプロに任せることは、本業に集中できるというメリットがあります。従業員のみなさんが効率よく能力を発揮できるようにサポートします」と藤原さんは言います。
また、個人向けには年金相談・裁定請求手続きを行っています。藤原さんが特に力を入れているのが、この個人向けの年金相談です。共済組合で8年間年金を担当していた実績があります。「老齢基礎年金や老齢厚生(共済)年金などの「老齢年金」は、実は一般的な「モデルケース」に該当する人はほとんどいません。なぜなら、老齢年金は年齢や性別によって支給開始の年齢や満額支給の年齢も異なり、保険料未納期間や保険料免除期間の有無、扶養家族の有無でも受給する年額が変わるからです。個人個人で受給額がまったく異なるため、コンサルティングが必要な場合も多いのです」と藤原さん。
実際に、「受給開始年齢になって、こんなに年金が少なかったのか」と驚く人も少なくないそうです。「現役のうちは、年金のことまで頭が回らないかもしれませんが、いろいろな対策が立てられるうちに、考えておきましょう。老後に不安を感じている方は、一度、ご相談ください」とアドバイスを送ります。
#chapter2
では、年金対策が必要なのは、どのようなケースでしょうか。「まず、老後の生活資金の不足額を把握することです。そのうえで公的年金だけでは老後の生活が成り立たない人は保険会社や共済などの個人年金保険や、国民年金基金、小規模企業共済、確定拠出年金等加入可能な制度の利用を考えた方がよいでしょう。また、年金受給開始年齢は段階的に65歳まで引き上げられています。企業は希望者を65歳まで雇用することが義務化されましたが、60歳以降の賃金は低下することが多く、60歳から65歳までの期間に収入が激減する恐れがあります。60代前半で受け取れる個人年金保険に加入したり、運用に自信があれば確定拠出年金に加入するなど、なんらかの対策を考えた方がよいと思います」
平成25年には65歳以上の人口が25%を超え、超高齢社会となった日本。年金不安も叫ばれる昨今、若年層を中心に公的年金の保険料を支払わない人が増えていますが、「この先、受給額は減額されることはあるかもしれませんが、年金がまったく支給されなくなることは考えにくい。未納期間が多くなるほど受給額も減ってしまいますし、万一の時に障害年金や遺族年金を受給できなくなるかもしれません。加入手続きや保険料免除申請の手続きが遅れている方は、少しでも早く手続きをした方がいいですね」と藤原さん。
ファイナンシャルプランナーでもある藤原さんは、「老後の資金についても、プランニングが可能」です。「年金ネットで、現時点で年金の受給の見込み額を確認できます。ご自身で知っておくことも大事です。ご相談いただければ、データを見ながら有意義なアドバイスをします」と言います。
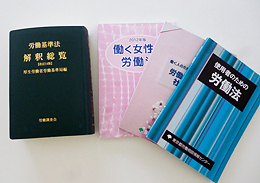
#chapter3
藤原さんは労働局の育児介護休業法を担当する部署に2年間在籍していました。その経験から、「育児介護休業法を通したワークライフバランスのコンサルティングにも力を入れていきたい」と言います。「法律は整備されても、職場の雰囲気によっては休暇を取りづらいこともあります。また長すぎる残業時間でプライベートな時間がなくなるのも問題。ワークライフバランスは重要な課題です。企業のオーナーの方々と一緒に制度を作っていけたらいいですね」
地方公務員退職後はツーリングで日本、オーストラリア、ニュージーランドを一周したという経験の持ち主でもある藤原さん。「日本とニュージーランドでは、資金稼ぎのために住み込みのバイトもしました(笑)。日本を周ったのが阪神淡路大震災の後で、知人に紹介された福祉団体の事務所に泊まり込んで西宮でボランティアも経験しました」。なかなかの行動力です。
そのエネルギッシュな一面で、「煩雑な年金をよりわかりやすくレクチャーできる社会保険労務士でありたい」と展望を話します。今後は、「年金について人々に知ってもらうため、学校などで社会保険教育の講座が開かれれば講師として参加したいですね。また、若手経営者を中心にワークライフバランスのコンサルティングも深めていきたいです」と抱負を語ってくれました。
(取材年月:2014年9月)
リンクをコピーしました
Profile

年金に強い社会保険労務士
藤原武志プロ
社会保険労務士
社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー 藤原事務所
共済組合で8年間年金を担当した実務経験により、年金問題のさまざまなケースに熟知。
\ 詳しいプロフィールやコラムをチェック /