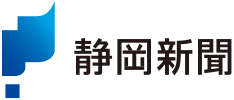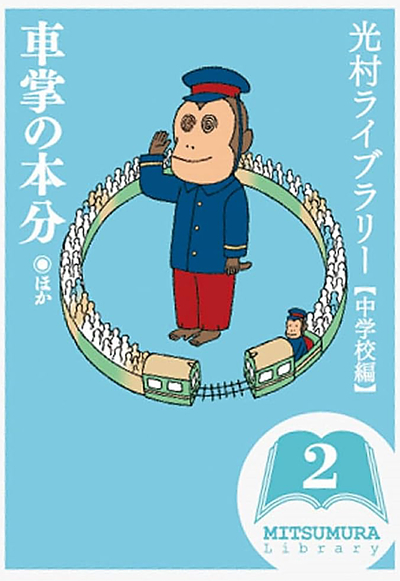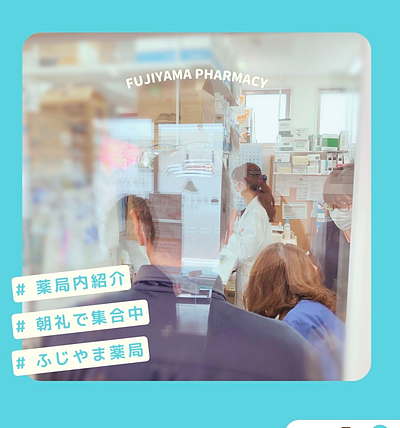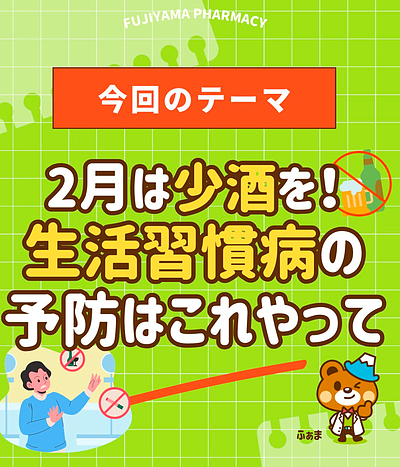アルコールにひそむ罠
富士市富士宮市にて在宅医療に携わっている薬剤師の栗原です。
目次
今日はこんな記事が、何と無く四時に目が覚めてトイレに行って開いたスマホから飛び込んできました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/cd278903d85446348633875188a2eef07a1ab454
日本維新の会の猪瀬議員が3/6の参議院予算委員会で発言した記事がありました。
ゼロベースで考えることはとても大切
いろいろなことを、インターネットなども活用して自分で調べられる時代になったこともあり、私たちもまた、専門的な領域以外のことについても何がしの知見を得られる時代です。
「ゼロベース思考」という言葉もあります。先入観なしに、利益相反を考慮しないで自分の感覚や主観、常識や良識を頼りに考えみてるということは、ともすれば専門的な縦割りが進むこの時代にあっては決して見失ってはならない視点だと思っています。
ただし、猪瀬氏は、こういう質疑をするに当たって、もしも医師会なり薬剤師会なりに質疑をした上でなら、もっと的確な指摘もあろうかと思います(ただその反面、既得権益の力学に取り込まれてしまう可能性もあるため、課題もあろうかと思います)。
この質疑について私なりに思うことは以下の点です。
1)「門前薬局」を悪者にするのは必ずしも正しくない
猪瀬氏が目にされた「門前薬局の立ち並ぶ様」というのはおそらく氏の地元の大きめの病院(病床300~)の前に立ち並ぶ大手調剤薬局群のことだろうと思われます。
「門前薬局」は、出来るだけ処方元の病院の近くにあることで、処方箋を受け取った患者様が利便性を持って利用できる薬局です。
病院の近くの利便性の良い場所にある薬局は、上手く使えば手早く、また処方箋に基づいたお薬の在庫をかなりの確率でもっている薬局なので使わない手はないでしょう。処方上の疑念のある点についても病院や処方医師との関わりも深いと考えられるため、安心です。
ところが、当然課題もあります。皆様も経験があるかと思いますが、大きな病院の薬局ではお薬を受け取るのに30分、場合によっては1時間近くかかることも珍しくありません。
理由は簡単です。薬局には1000単位の種類のお薬が準備されており、それぞれの処方に基づき、棚から調剤師が1つ1つ取り上げているという物理的な課題があります。病院に対して、通常5名から10名の薬剤師を抱えている薬局の持っているキャパシティーは、決して十分とは言えないのです。
「門前」にあることで処方箋がその店舗に集中することで大手の薬局が利益をあげすぎてしまう点についてはこれまでも調剤報酬の点から改正がされてきました。この問題に対して、全く検討されていないのではありません。薬局ならびに薬剤師が得られる利益が、果たして薬剤師や薬局への社会的意義の面から見て、妥当な評価がされているのかどうかが大切なのです。
2)「医薬分業」の趣旨を正しく取られることが大切
「医薬分業」は、医師と薬剤師の働きを切り分ける、西洋型の近代医学・薬学の世界では基本的な役割分担の考え方です。
医師は主に「診断」つまり病名の決定を行い、それに基づいてお薬の処方箋を書きます。それに対して薬剤師は、この処方箋に基づいて医薬品を準備し、その処方がその患者様にとって相応しいものであるかを、患者様への聴取を通して検証するのです。つまり役割分担が行われています。
西洋ではこの医薬分業の勤めは完全に切り離されていますが、日本の場合、特例的に医師がお薬を「調剤」することが認められています。
問題はこの特例が幅を効かせてしまってしまうことがあるということです。
結果として、薬剤師の責任が軽視され、あたかも薬剤師の勤めはお薬を棚からピッキングすることが主眼に置かれるような時代もあったのです。それでは薬剤師が本来持っている知見のポテンシャルが十分に生かされることにはならないのです。
3)薬剤師の働きを正しく理解していただくことが大切
大学の薬学部では、基礎物理化学、薬物動態学、薬理学など、医師の養成機関である医学部ではそれほど深く学ぶ機会のない分野の教授が行われています。特にお薬が体に入ってからどのように吸収、代謝されていくかを学ぶ薬物動態学は、薬剤師の専売特許とも言えます。
またお薬の「相互作用」という、複数のお薬を服用している場合にお薬相互が影響をもたらして、作用の減弱並びに増強をもたらしてしまうこともあります。これも薬剤師の専門分野です。
医師もお薬の相互作用や体内動態も、全く治験を持たないわけではありません。薬理学もそれなりに大学で学ばれます。
でも多くの場合、若い医師は現場に出て、すでに現場にいる経験豊かな薬剤師の指摘(疑義照会)を通して薬理学や薬物動態の知見を深めているというのが実情と言えます。薬剤師は自らの知見を医師に提供し、還元して、より相応しい薬剤の処方を医師に促しているということができるのです。
4)服薬管理指導料はお薬手帳に直接に依存するものではない
この点についてはすでにこちらでも解説されています。
「服薬管理指導料」は、何もお薬手帳に依存するものではありません。お薬手帳は服薬指導を薬剤師が行うに当たってとても有効なツールですが、もしなかったとしても薬剤師は、患者様からの聴取によって服薬指導を行なっているのです。
医師に色々と自分の症状をお伝えした上で、改めて薬局で色々質問されるのは二度手間だし意味のないことだと感じる人もいるでしょう。
でもあえて、その二度手間を踏むことで、思いもよらない処方ミスが判明することがあるのです。
患者様が医師に伝えた内容が十分に医師に伝わっておらず、欲しかったお薬が処方箋に載っていないことは珍しいことではありません。
一旦自宅に帰ってから、改めてそのお薬を追加でもらうことは難しいと言って良いでしょう。
その点、薬剤師からの問いかけが、薬局内での問題の発覚に繋がり、薬剤師から病院に問い合わせることでお薬の変更がなさらることは日常的な出来事です。「服薬指導料」は、このような薬剤師の良い働きを正当に評価し促すために加算されるものとも言えるのです。
「服薬管理指導」は、薬剤師が患者様との簡単な会話の中で、白鳥が湖の水面の下で必死に動かしている脚のようなものとも言えます。
簡単な体調変化、処方内容の変化に伴って薬剤師側で推測可能な状態変化についての質問などは、薬理学的、病理学的、薬物動態学的な知識があったこそ可能となります。
もしも「服薬管理指導」が必要ないのであれば、お薬のピッキングとお渡しを機械化出来るかもしれません。
でも、処方内容がそもそも妥当なものか?患者様の自覚症状など、薬剤師としての専門的な観点から行って何か気になる点はないか?など、責任を伴うお薬のお渡しをするためには人間の手は当面、不可欠なものです。患者様についての情報をたとえばカメラで記録し、情報分析し、聴取内容もコンピューターが聴き取って妥当に判断することは、当面は出来ないでしょう。
5)お薬手帳の意義を理解していただくことか大切
猪瀬議員は、お薬手帳ではなくてマイナンバーカードに紐付けされた処方情報があれば良いではないか?服薬管理指導料など要らないではないか?と考えておられるようです。
でも服薬管理指導料はお薬手帳に依存するものではありません。またマイナンバーに紐付けられた情報の閲覧が可能であるとしたら、薬剤師はそれを活用してより良い服薬指導に取り組むだけです。
薬局で皆様がお支払いになる「お薬代」は、単にお薬「そのもの」お代金に限るものではありません。お薬(薬局)の管理・運営上の薬局体制の要件達成度から生じる「調剤技術料」と呼ばれる加算がありますし、ここまで言及してきた「服薬管理指導料」の他に「かかりつけ薬剤師(薬局)」には「かかりつけ薬剤師指導料」、在宅への配薬を前提とした「訪問薬剤管理指導料」などがあります。
これらの加算点数は、薬局側が独自に勝手に定めているものではなく、厚生労働省によって定められる「調剤報酬」によって一律に定められるものです。
薬剤師は、単にお薬を処方箋通りに棚からピッキングして袋詰めしているだけのお仕事をしているのではありません。調剤の働きにおいて、薬学的治験を生かしてその処方の内容が個々の患者様にとって妥当なものかどうか検証する働きをさせて頂いているのです。