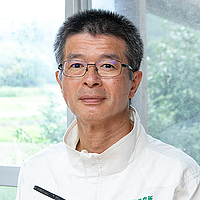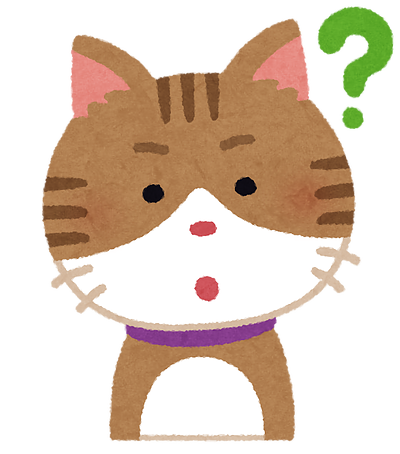SPring-8に来られる先生方のサポートがしたいところですが…
この『雑誌会の部屋』は、化学系の雑誌を中心に独断と偏見で研究例を選び、不定期でご紹介するコーナーです。
A Biochemical Corrosion Monitoring Sensor with a Silver/Carbon
Comb Structure for the Detection of Living Escherichia coli
ACS Omega 2023, 8, 43511−43520
銀が硫黄で腐食されることで発生する電流の変化を利用して、大腸菌を検出しようというお話です。
(本文)
https://pubs.acs.org/doi/epdf/10.1021/acsomega.3c03632
(追加情報)
https://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/acsomega.3c03632/suppl_file/ao3c03632_si_001.pdf
電気的なセンサを用いて、大腸菌を検出させる研究例は過去にもあったようです。
これは、培養とかして、他の方法で検査するより、簡便且つ短時間で測定できるメリットがあるからのようです。
平板型電気化学チップを用いた大腸菌の直接検知
https://www.ushio.co.jp/jp/technology/lightedge/201412/100498.html
O157等の細菌の迅速検出が可能なセンサ
https://www.osakafu-u.ac.jp/press-release/pr20191028/
既に開発され、市販もされているACM(Atmospheric Corrosion Monitor)型腐食センサ(通称ACMセンサ)と呼ばれる検出器を大腸菌検出に応用しようとした研究例です。
まず、ACMセンサについて、
ACMセンサ計測の原理と概要
https://www.syrinx.co.jp/acm-spec/about-acm.htm
このACMセンサ、福井県の会社も開発、実用化したようです。
⼤気腐⾷モニタリングセンサ「ACMセンサ」
https://www.fklab.fukui.fukui.jp/kougi/tecinfo/results/52.pdf
応用例その1
福井県における炭素鋼の大気腐食性評価
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcorr/62/11/62_426/_pdf/-char/ja
応用例その2
カーボンカソード ACM 型腐食センサの電流特性
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcorr/68/8/68_212/_pdf
既に上記資料にACMセンサの概要が書かれていますが、図1で改めて見ることにします。
ここでは、BCM(biochemical corrosion monirtoring)センサと称してありますが、実質ACMセンサと思われます。
図2はセンサを組み上げた測定系の写真と見取り図です。
それで、今回の研究例は結局何をやっているか?と言えば、腐食されて、AgからAg2S( https://surfacenet.de/files/kristall_daten.php?crystal=19)に変化し、ガルバーニ電流が発生し、それを測定しようということです。
ガルバーニ電流について、『ガルバーニ電流は、通常異なる種類の金属が触れ合うと発生します。』とあります。
https://hirazawa-dc.com/1505galvanie/
結果です。
図3は大腸菌溶液などにセンサを浸した場合の、時間とガルバーニ電流の関係についての結果です。
大腸菌の数は、CFU/mLという単位で表されます。
CFUについては、
CFUとは、Colony Forming Unit(コロニー形成単位)といい、細菌検査で用いられる単位です。細菌を培地で培養し、できたコロニー(集団)数のことです。
(例)50 CFU/100mL = 100mL中に細菌が50コロニーあります。
https://www.legiosearch.com/faq/detail04.php
大腸菌については、E. coli DH5αを使っていると書かれてあります。
DH5αについては、『DH5α株はクローニングに最もよく使用される大腸菌株の一つです。』とあります。
https://www.funakoshi.co.jp/contents/8342
しからば、クローニングについては、『クローニングとは,ゲノム編集等の遺伝子操作を実施した細胞集団の中から、特定のDNA配列を持つ細胞を検出・特定し,同じ遺伝子型となる細胞集団を作製すること(クローン株樹立)です。』とあります。
https://www.an.shimadzu.co.jp/industries/life-science/cell/0022020/index.html
今回の研究例では、ごく一般的に多用されている大腸菌として選ばれたと考えて良さそうです。
まず、LB培地中に生きている大腸菌の数が10^8 CFU/mLの場合です。
測定開始から20分後に電流は上昇し始め、およそ120分で電流値は最大の660nAまで上昇したようです。
なお、LB培地については、『LB培地は大腸菌の培養に適した培地であるが,一般細菌全般の培養にも広く用いられている。』とあります。
https://www.sbj.or.jp/wp-content/uploads/file/sbj/8904/8904_yomoyama_1.pdf
続いて大腸菌の数が10^7 CFU/mLと低くなった場合は、開始後100分あたりで電流は上昇を始め、およそ220分後に約400nAで最大となったようです。
更に大腸菌の数が10^5 CFU/mLの場合ですと、140分で電流は上昇を始め、およそ390分後に約300nAで最大となったようです。
このように、大腸菌の数と電流の立ち上がり時期と最大値には相関があったようです。
これに対して、生きていない大腸菌を使用した場合と生きているけど、HEPES bufferを用いた場合は電流の変化が観測されなかったようです。
なお、HEPES bufferについては、『水によく溶け、2.25 mol/l(0℃)で飽和する。有機溶媒にはほとんど溶けない。pKa=7.55、pH6.8~8.2の緩衝液を作るのに適する。HEPESはグッド緩衝剤(Good's buffer:グットバッファー)の一つで、その中でも代表的な緩衝剤である。細胞培養、組織培養など生化学分野で広く使用されている。』とあります。
https://www.dojindo.co.jp/products/GB10/
死んでしまった大腸菌はまだしも、生きているのに、緩衝液を使うと、銀の腐食が起こらず、ガルバーニ電流が観測されなかったことついては、何がどう違うのか?疑問です。
図4は大腸菌の量をガルバーニ電流と分光光度計 U-3900
( https://www.hitachi-hightech.com/jp/ja/products/analytical-systems/spectrophotometers/uv-vis-nir/u3900.html)で600nmの吸光度(OD600)を測定した結果を比較した図です。
大腸菌の数は10^5 CFU/mLだったようです。
まず、吸光度を測定することについてです。
下記には『細菌培養液の光学密度(OD)測定は、微生物学において使用される一般的な手法です。研究者らは、これらの測定を行うために紫外可視分光光度計を使用してきましたが、この測定は、実際にはサンプル(培養液)に吸収された光の量ではなく、培養液によって散乱された光の量に基づきます。
(途中略)
培地中の細菌増殖の標準段階(誘導期、対数期、静止期、および死滅期)はよく知られており、対数期は細菌が可能な限り急速に分裂するフェーズとして認識されています1。通常、細菌増殖をモニターするために、分光光度計を使用して、600 nm(OD600)で光学密度を測定します。』とあります。
https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/MSD/Application-Notes/an-035-uv-bacterial-optical-density-an035.pdf
ここで再び図4は、10^5cfu/mLの大腸菌水溶液を用いた菌応答試験における、試験セル内のガルバーニ電流および大腸菌水溶液のOD600の変化を示しています。大腸菌水溶液のOD600は、試験開始から60分の誘導期間を経て急激に増加し、その後240分頃から増加率が低下し、徐々に増加したようです。OD600の変化から、大腸菌の増殖速度は60分から240分までは対数期、400分以降は静止期の手前の減速期と考えられるようです。一方、ガルバーニ電流は、試験開始後140分までは10 nA未満でしたが、約160分から増加し始め、390分に最大値を示し、その後減少したようです。ガルバーニ電流は、OD600が増加し始めてから約100分後に増加し始めたことになります。このように、ガルバーニ電流は大腸菌の対数増殖期に増加し始め、静止期に移行する前の減速期に最大に達したようです。
なお、図4に示すように、対数増殖期における測定セル中の大腸菌の倍増時間 (τ) は27分であり、同一細菌溶液を電極センサに接触させずに37℃で培養した場合も27分であることを確認したみたいです。したがって,測定細胞中の大腸菌と電極センサを接触なしで培養した大腸菌は同じ速度で増殖し,電極接触による増殖阻害はないことが確認できたようです。
更に10レベルの大腸菌溶液を調製し、初期菌数の範囲は0~10^8cfu/mLとしました。この大腸菌溶液を用いて、Ag/Cセンサの細菌応答試験を行い、大腸菌数ごとのAg/Cセンサのガルバーニ電流変化を図5に示すことができたようです。大腸菌の初期数が0〜10^8cfu/mLの範囲にあるすべての溶液において、Ag/Cセンサのガルバーニ電流値は、大腸菌溶液を滴下した後、しばらくは10nA以下で推移していたようですが、所定時間後に徐々に増加し、最大値まで増加した後、徐々に減少したようです。大腸菌の初期数が多いほど、ガルバーニ電流値は早期に上昇し、ピークも早く迎えたようです。試験後、ガルバーニ電流値の増加を示したAg/CセンサのAg電極表面は、茶色に着色したようです。この着色の強さは、初期の大腸菌数が減少するにつれて減少したようです。(追加情報、図S2)。大腸菌の初期数が減少するにつれて、Ag電極上の着色生成物の量が減少したものと推測されます。
図6は、細菌応答試験における電流曲線から得られたT20(20nAに達するまでの時間)と大腸菌初期数の対数との関係を示し、電流曲線のT20の平均値(n=5)、μを記号、μ±σ(σ:標準偏差)をエラーバーの上下端としています。変動係数は、初期大腸菌数が10^7cfu/mLの場合は<20%、それ以外は<10%であり、センサ測定の再現性が高いことが確認されたようです。
大腸菌の初期数が1~10^8cfu/mLの場合、T20は大腸菌の初期数の増加とともに減少する傾向が見られたようです。初期大腸菌数(cfu/mL)の対数とT20(min)の間には高い相関が認められたようです。
ここで、大腸菌の初期数を X とすると、式 2 の直線関係(R2 = 0.984)が得られたようです。
大腸菌溶液の1cfu/mLの場合、T20は560分であったようです。電流曲線において大腸菌初期数と高い相関を示した項目は、100nAに達するまでの時間(R2=0.997)、最大電流値に達するまでの時間(R2=0.985)、最大電流値(R2=0.572)、1000分間の電気量(R2=0.776)であった。したがって、式2はT20から生きた大腸菌数を求めるための検量線として使用できそうです。
図7は、10^8cfu/mL大腸菌溶液中におけるAg/Cセンサの腐食電位とガルバーニ電流の時間変化を示すものです。腐食電位は測定開始直後の230 mVから30分後には-190 mVまで減少し、同時にガルバーニ電流が発生したようです。pH7付近の大腸菌溶液の初期腐食電位に相当する約230 mVの電位では、25℃におけるAg-S-Cl-CO2-H2O系のQpotential-pH平衡図に示すように、安定相はAg金属であるようです。しかし、30分後に観察された-190 mVの腐食電位では、安定相がAg2Sであったようです。これは、Ag/Cセンサのアノード表面でAgが硫化反応を起こし、その結果ガルバーニ電流が生成したことが示唆されることになります。
上記のように、Ag/CセンサのAg電極表面は、茶色に着色したようです。そこで、着色したAg電極としていないAg電極を比較しています。
図8は、カソード剥離実験で得られたAg/Cセンサの着色Ag電極面と非着色Ag電極面のカソード還元曲線のようです。着色したAg電極表面の電極電位は、腐食電位が 40 mVから減少し、還元時間が 380 sまでの間、約-530 mVで一定となり、その後再び急激に減少したようです。電極表面の着色の消失は、Ag金属電極電位が約-756 mVのときに目視で確認されたとあります。図中に示された約-530 mVのプラトー電位(電位が平坦になる電位、 https://www.toyo.co.jp/material/faq/detail/id=14896)は、Ag2S膜の還元に起因するものであったようです。Ag電極表面に析出したAg2Sの量は、還元時間から246 nmolと計算されたようです。その膜の平均厚さtは、M=247.8 g/mol、ρ=7.32 g/cm3、n=2(Ag2Sが還元されてAg金属になるため)の式1から、26 nmと計算されたようです。
なお、着色したセンサは、108cfu/mLの大腸菌水溶液を用いた細菌応答試験でガルバーニ腐食させて作製したようです。その時のガルバーニ電流の積算電荷は48mCであり、Ag電極表面に249nmolのAg2Sが析出したことが計算されたようです。したがって、Ag電極表面に析出したAg2Sの量は、カソードから剥離したAg2Sの量とほぼ同じであることがわかったようです。Ag/Cセンサの未着色Ag電極表面にはAg2Sは析出しなかったようです。未着色Ag電極表面の電極電位については、腐食電位が30 mVから急激に低下し、20秒後には約-1000 mVに達したようです。陽極表面でのAg2S膜の形成は、Ag電極表面での硫化反応の発生を裏付けているものとなるようです。Ag2Sの水溶液への溶解度は6.15×10-13g/Lと著しく低いので、Ag2Sは大腸菌溶液中で生成した直後にAg電極表面に析出すると推定されるみたいです。
表2は大腸菌の初期数が10^8cfu/mLの場合における、各種イオンの濃度、pHが書かれています。開始後、120分の時点では、NO3-とNH4+の濃度が増えたようですが、その他のイオンには変化がなかったようです。また、TSI培地を用いた大腸菌培養では、培養開始から24時間後に0.36μMのH2Sが生成したことが報告されているようです。
ちなみにTSI培地については、『TSI培地には“0.1%”という極低い濃度のブドウ糖しか含まれていない点がポイントです。』とあります。
https://www.kanazawa-med.ac.jp/~kansen/situmon3/tsi-baichi.html
同様に、今回の研究例でも、大腸菌が代謝したH2Sなどの硫黄化合物が増殖過程で大腸菌液中に放出されているようです。これらの硫黄化合物が、Ag/CセンサのAg電極表面を硫化するものと推測されます。大腸菌は、L-システイン脱水素酵素が触媒となってL-システインを分解し、ピルビン酸、NH3、H2Sを生成する代謝経路を持つようです(式3)。
これについて、『シスチンが多量に含有している培地では一般的な大腸菌も“硫化水素”を産生します。』とあります。
http://www.kanazawa-med.ac.jp/~kansen/situmon3/daichokin-gas.html
更には、
『例えば大腸菌は有機の「シスチン」から硫化水素を産生しますが, 無機の硫黄源からの産生は出来ません。でも, サルモネラはどちらの硫黄源からも硫化水素を産生できます。ここで, サルモネラだけではなく, 腸内細菌科に含まれているほとんどの菌は多かれ少なかれ「硫化水素」を産生するのです。』とあります。
http://www.kanazawa-med.ac.jp/~kansen/situmon3/salmonella-tsi.html
今回の研究例では、トリプトンとアミノ酸を含むLB液体培地を大腸菌溶液に添加したため、大腸菌が代謝したH2Sは、一部はアミノ酸などと結合しているものの、遊離のH2Sとして存在すると推定されるようです。
トリプトンについては、『トリプトン(Tryptone)とは、カゼインに対してトリプシンを作用させて作成される、加水分解物である。』とあります。
https://chiyousei.co.jp/product/cat09/tryptone-dif-500g.html
さて、図9aは、大腸菌の初期数が10^6cfu/mLの場合における、細菌反応試験におけるAg/Cセンサのガルバーニ電流値と試験溶液の遊離H2S濃度の時間変化を示しています。大腸菌溶液のクロマトグラムも図S5に示されています。大腸菌溶液中の遊離H2S濃度は、試験開始から120分までは約0.022 μMのままであったが、160分にガルバーニ電流値が21 nAに増加すると遊離H2S濃度は0.058 μMに増加し、300分にガルバーニ電流値が376 nAに達すると0.70 μMにまで増加したようです。その後、ガルバーニ電流値が減少するにつれて遊離H2S濃度も減少したようです。図9bは、大腸菌溶液中の遊離H2S濃度とガルバーニ電流値の関係を示しており、ガルバーニ電流値と遊離H2S濃度は強い直線関係(R2 = 0.991)を示したようです。
図10は静止電位と電流密度の関係を示していますが、かなり見づらい図ですが、順に見て行くことにします。
まずは黒線でLB液体培地中のAg電極に関するものです。アノード電流密度は、静止電位0.23 Vで急激に増加し、0.4 V以上で一定値となったようです。なお、0.30V付近でのアノード電流密度の増加は、平衡電位Eeq (Ag/AgCl, 0.085 M Cl-) = 0.29Vと一致したようです。静止電位から1.0Vまで分極したAg電極表面の析出物の主成分は、蛍光X線分析によりAgとCl元素として検出されたようです。したがって、Ag/AgCl反応(式9)は、LB液体培地と大腸菌溶液が0.085 M NaClを含むことから、Ag電極の表面で起こると推測されたようです。
次にLB液体培地中のC電極(黒点線)では、カソード電流密度は、静止電位0.23V以下から徐々に増加し、-0.5V以下で約10μA/cm2の電流密度を示したようです。
更に大腸菌液中のAg電極のアノード電流密度(オレンジ色線)は、-0.21 Vの静止電位から急激に増加し、-0.17 Vから約0.17 Vの電位範囲で400 nA/cm2以上の値を維持したようです。更に電位を上げると、LB液体培地中のAg電極のアノード電流密度と同様に再び急激に増加した後、0.4 V以上において一定値に達したようです。静止電位-0.21 Vは、LB液体培地中のAg電極の静止電位より0.44 V低く、平衡電位Eeq(Ag/Ag2S, pH 7) = -0.15 V以下であったようです。
これらの結果は、図7に示した腐食電位値の変化を裏付けているようです。大腸菌溶液中のC電極のカソード電流密度は、静止電位0 Vから徐々に増加し、-0.5 V以下で約1 μA/cm2の電流密度を示したようです。大腸菌から放出された遊離H2Sは、H2Sの酸解離平衡(式5)のため、pH約7の大腸菌溶液中では主にH2SとHS-の形態で存在するようです。静止電位から0.2 Vまで分極したAg電極表面の析出物の主成分は、蛍光X線分析では、AgとS元素として検出されたようです。したがって、大腸菌溶液中のHS-とH2SのAg電極との反応(式6および式7)は、Ag電極表面で起こると考えられるようです。
大気条件下での水溶液中の主なカソード電流は、溶存酸素の還元反応(式10と11)とH+の還元反応(式12と13)と考えられるみたいです。pH約7の水溶液では、式11と13の反応が優勢であり、その平衡電位はそれぞれEeq(4OH-/O2, pH 7) = 0.82VとEeq(H2/2H2O, pH 7) = -0.41Vとなります。したがって、図10に示したC電極のカソード電流は、静止電位から約-0.41 Vまでの電位範囲では溶存酸素の還元電流(式 11)と推定され、-0.41 V以下ではH+の還元電流(eq 13)が加わるみたいです。
分極試験は大気圧下で行ったため、試験液には十分な酸素が供給されていたようです。しかし、大腸菌溶液中のC電極のカソード電流密度は、0~-1.0Vの電位範囲において、LB液体培地中のC電極のカソード電流密度よりも低かったようです。これは、細菌の増殖活動により大腸菌溶液中の溶存酸素が減少したためと考察しているようです。
H2SとHS-を含む大腸菌溶液では、Ag/AgS反応の発生によりアノード電流が明らかに増加したようです。(式6と7)大腸菌溶液中でのAg/Cセンサのガルバーニ電流値の増加は、大腸菌によって代謝されたH2SとAg電極の反応によるAg電極のアノード電流密度の増加に起因するようです。したがって、電極の反応機構は以下のようになるようです。
(1)Ag/Cセンサの陽極表面では、式6と式7に示す酸化反応が起こる。
(2)一方、陰極表面では、pH約7の大腸菌溶液中で溶存酸素を含む還元反応(式11)が起こり、電極間にガルバーニ電流が発生する。
さて、図9aに示されたガルバーニ電流値の最大値376 nAの場合、120秒間Ag/Cセンサに電流が流れると、センサの総電気量は46 μCとなるようです。46μCの電気量を式6の反応によって発生する電流に換算すると、ファラデーの法則に基づき、10mLの大腸菌溶液中の0.023μMに相当する0.23nmolのH2SがAg電極と反応して0.23nmolのAg2Sを生成したようです。図9は、大腸菌溶液が376 nAで0.70 μMの遊離H2Sを持つことを示しています。そんなこんなで、大腸菌溶液中に存在した遊離H2Sの約3.3%がAg電極と反応し、ガルバーニ電流値を発生させたと考えられます。Ag/Cセンサは、大腸菌の増殖によって増加した遊離H2Sと反応し、ガルバーニ電流値が上昇します。T20は、大腸菌溶液中の遊離H2S濃度がAg/Cセンサの検出限界を超えるまでに要する時間と見積もられました。大腸菌1個あたりに代謝される遊離H2S量が等しい培養条件下では、大腸菌の初期数が多いほど大腸菌溶液中の遊離H2S濃度の上昇速度が速くなり、T20は短くなる傾向にあるようです。したがって、大腸菌の初期数の対数とT20の間には、式2に示すような直線関係が成立することになるはずです。
所感です。
元々開発していたセンサを大腸菌の検出に応用したというお話でした。
結局は電流値を測定していることになるのですが、それが全く違う分野でも同じ現象を拾うということは興味深いところです。
しかも、生きている大腸菌のみが検出されたことも面白いと考えます。
ただ、今回の研究例では、大腸菌は一種類のみで、他の種類の菌の場合はどうなるのか?
選択性はあるのか?自然界のように、二種類以上の菌がいる場合はどうなるのでしょうか?続きの研究が進むことを期待します。