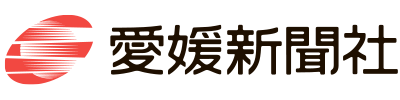療育について
私が保育士の時に(約30年前)、園長先生や先輩方に多くのことを学びました。
その時に、難病をお持ちのお子さんを園に預かっており、その子のお母さんが元保育士さんで度々お子さんの様子を見に来られました。そのたびに、お子さんとのかかわり方を見せてもらい、「子どもの人権」に対しての話を聞かせて頂き、本当にたくさんのことを学ばせていただきました。
その方は、子どもに自身の病気のことをすべて正しく伝え、自らが考え選択し、責任をもって生きられるように育てておられました。
また、園全体で、モンテッソーリ教育を学びに行き、みんなで自由保育を学びました。
モンテッソーリ教育を取り入れている園では、「子ども」と呼ばずに「小さな人」と呼んでいました。
身体が小さく、この世の経験値が少ないだけで、しっかりと自分の考えをもった一人の人間である、という子どもの人権に対する教えを受けることができました。
その人権感覚は、その後の私の子育て感に、最も重要なものとなりました。
わが子を一人の人として尊重し、この世を生きる対等な存在として育てました。ただ、この世のルールや社会性に関しては、まだ未熟である人として、生きていくのに必要なマナーは環境を整え、躾をしていきました。
食事中は、きちんと座って最後まで食べる、生活の流れの時間を毎日なるべく同じにし、良い習慣をルーティン化する。早寝早起きに努める。
そうすることで、時間や場所など枠組みの中で自由を得る、自分で考えて自ら行動を起こす、という基本が出来上がっていきました。
では、声かけは、どのようにしたらいいのか。
これも保育士の時に研修を受けた「親業」の考えを利用させてもらいました。
「親業」とは、子育ては親という職業であるという考えの元「親業訓練協会」があります。
子どもとの会話には受容と共感が大切です。
ジャッジや教訓を言うのではなく、すべて受け止めます。そして、「その時どう思ったの?」「もっと詳しく教えて」など、能動的に聞き、子どもの考えや行動に子ども自らが気が付くように会話をします。
親や大人の思いを伝えるときには、「私メッセージ」で伝えます。
①行動→②影響→③感情で話してください。
【例】
学校から帰ってカバンを玄関に置きっぱなしの時には
まず受容・・子どもが何故そうしているのかを聞きます。
この後、親メッセージではなく、一人の人間として「私メッセージ」で話します。
①でも、玄関にカバンを置いていると
②荷物を持って帰ったお母さんは転びそうで
③怖いなあ。困るなあ。
子どもの発言や考えがとても楽しいと思って会話をしてみてください。
子どもの考えに質問をしたり、私の経験を話したりしていると、だんだん考えが深まり、一人の人間として尊重し合いながら互いに成長していけます。
また、「えらいね」「すごいね」とやたら褒めなくていいと思います。褒められるために「いい子」になり、しんどくなります。本当の褒め言葉は「共感・認める」だと思います。
「その考え、私もいいと思うよ。」
「素敵な考えが浮かんだね。」
「帽子が汗で濡れるくらい頑張ったんだね」
私はテレビを持っていませんし、子育ての間は「ゲームは大人になってから」というルールにしていましたので子どもとたくさん会話をしました。
生き抜く力をもつとは、自分の考えをしっかりと発言でき、自分の考えを実行できるという主体性・実行機能が必要だと思います。私の子ども達は、決して、いい大学に行ったり、お金儲けがうまかったりしませんが、ただ、生き抜く力だけは持っていると思います。
今日も、読んでいただきありがとうございました。
次回は、障がい児という考えについて書きます。