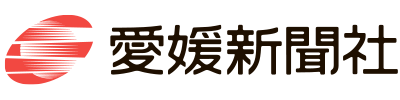療育について
今日は、子どもが主体的に生きるというテーマで書いていきます。
子どもの主体性とは、自ら考え進んで行動し、責任と目的をもって行動する態度や様子のことです。
まずは、子どもは自ら「やりたい」という気持ちを持っています。
赤ちゃんが足の指をなめる行為も、2歳頃にみられる「いやいや期」も、自分を知りたい、自分でやってみたい、という、心の底から湧き上がる主体性です。
私が短大の幼児教育課程で学んだ言葉「心情、意欲、態度を育てる」これは、保育士になっても、わが子を育てるときにも、多くの自閉症児と過ごす中にも、忘れたことはありません。
その子、その子の心の思いを知ろうとし、その子の意欲を引き出し、とことん納得するまで取り組む環境を整えること、これが子育てにおいて最も大切です。
そして、この環境を整えるときに必要なのが、1回目のコラムに書いた「本当の自由」を得られる場所なのです。自由の枠は、大人の経験値によりますし、心や道具の準備によります。ゆとりをもって行ってください。学ぶのは子ども本人であり、大人は教えるのではなく環境を整え、自由を得られる枠に徹し、見守る存在となることが大切です。
たとえば、大人の真似をして「お料理をしたい」と言ってきたとしましょう。
エプロン、踏み台、子ども用包丁、ピーラーなど用意します。
選ぶのは子ども本人です。
「踏み台はいらない」と言えば無しでやってみましょう。「やっぱりいる」と言えば、自分で準備してもらいます。やってみて自分で発見することが大事です。作る料理を伝え(これは決まっていると伝えましょう)材料を一緒に考えます。野菜の名前を言いながら一緒に準備してもいいですね。
それぞれの食材の調理の方法を伝えます。どれをするかは子どもが自ら選びます。
皮むきやカットなど取り組み始めたら口出しはせずに見守りつつ、時間がかかりそうならどの食材を手伝っていいか交渉してみてください。
ここで大事なことは、自ら「やりたい」と言ってきたことですから、どこまでやるのかも子どもに任せてください。大人が主体にならない、子どもを焦らせたり、「だから言ったでしょ?」と言ったりしない。子どもは、とことん行うことで、満足します。その満足が「自己効力感」を育てます。人に認められる、褒められることで得られる自己肯定感ではなく、自分の持てる力を自分が認識する力です。ただ、嫌なことを避けようとするときには、「自分が使ったものも私(親)が洗うのは何か違うと思うよ」などのように人として話してください。気持ちが納得したら終わってもいいけど終わり方は伝えてあげてください。
これが育つと実行機能が育ちます。実行機能とは、いわゆる「やる気スイッチ」です。
私の子ども達は小学3年生では、家族の料理を作ってくれていました。最初は一緒に作りましたが、そのうち、子どもが自ら作り始めたら「洗濯をたたむから、お料理おねがいね」とその場から離れるようにしていました。「何か困ったことがあったら言ってきてね」というスタンスでした。傍にいると、ついつい口出しをしてしまいますから。
その後、中学、高校では、全く料理をしなくなりましたが、それを責めることもなくきました。現在、一人暮らしで調理をしているようですし、親が寝込むと料理をしてくれています。(笑)
次回は、子どもの主体性を引き出す言葉かけです。