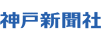コラム
「やる気」を知る
2021年8月18日
はじめに
「やる気がでない」と口にしたことはありませんか。勉強にしても、仕事にしても、人間関係の構築にしても、糖尿病の療養行動にしても、「やる気」がでればうまくいくという場面は少なくありません。わかっていてもなかなか簡単には出てこない「やる気」を引き出すためにはどうすればよいのでしょうか。そこで、今回は「やる気」について考えてみたいと思います。
「やる気」と「動機づけ」
「やる気」とは、物事を積極的に進めようとする気持ちのことです。心理学では、これをモチベーション(動機づけ)の問題として研究されています。
動機づけは、私たちが物事を実行しようとする際の大きな動力源になります。行動が生起され、維持され、方向づけられるプロセス全般に大きく関わります。
糖尿病療養行動に関連して考えてみましょう。
糖尿病治療の目標は、糖尿病でない人と変らない豊かな人生を送ることです。糖尿病と診断されますと、その目標を達成するために、何が必要なのかを調べて、準備して、取り組みを始めます。これが「生起」です。
糖尿病に対する療養は続けていく必要があります。嫌になったり、うまくいかなかったりするかもしれません。これらを「維持」していくことにも動機づけは大きく関与します。
さらに、転職や引っ越しなどを機会に、療養行動を大きく見直さなければならなくなることがあるかもしれません。新しい治療法が必要になることもあります、そんな時に、療養行動全体の方針を考え、調整するということ(方向づける)にもやる気は重要な要素です。つまり、モチベーション(動機づけ)をどのようにコントロールするのかが、行動の成否に影響を及ぼします。糖尿病療養行動にも、糖尿病でない人と変わらない豊かな人生を送るためにモチベーション(動機づけ)が重要な要素になってくるのです。
やる気をコントロールすることの難しさ
それでは、その大切なやる気をどうやってコントロールすればよいのでしょうか。やる気スイッチという言葉が流行したこともありましたが、やる気を自在にコントロールすることはたやすくありません。それは、やる気自体がたいへん複雑な概念から成り立っているからです。
例えば、運動に対するやる気を考えてみましょう。オリンピックに触発されて、やる気がでてきたので、毎日10km走り始めたとします。急に過度な運動を行っても、身体を痛めてしまったり、辛くて三日坊主で終わってしまったりする可能性が高いのではないでしょうか。この時のやる気は、何が問題だったのでしょう。例えば、やる気はあっても量が充分ではなかったのかもかもしれません。あるいは、やる気はあっても、方向づけ(やる気の質)が悪かったのかもしれません。このように一言で、やる気と言っても、いきなり結果に直結するものではなく、やる気の質や量といった、やる気の成分が行動の成果に直結してきます。
さらに、やる気は様々な要因に影響され、刻一刻と変動していきます。食事には興味があっても、運動には興味がない。運動には興味がなくても、先ほどの例のようにオリンピックによって、急に運動に対するやる気がこみ上げてくることもあります。一緒に歩いてくれる人がいれば、やる気になる場合もあるでしょうし、雨が降っていればやる気が起こらないという場合もあります。さらには、何にでも前向きに取り組む人もいれば、なかなか前向きになれない人もいて、個性の要素が強いこともやる気をコントロールすることを難しくしています。
モチベーションを決める要素
このようにコントロールすることが難しいやる気を左右する要素として、心理学的には4つの要素の存在が明らかにされています。
1.欲求
欲求は、生理的欲求と心理的欲求に分けられます。食欲を満たすために、スーパーに買い物に行くといった場合は、生理的欲求がスーパーに行くというやる気を引き出しています。
心理的欲求は、マズロー博士が提唱した欲求五段階説が有名です。
第一段階:生理的欲求
第二段階:安全欲求 安全な暮らしがしたいという欲求
第三段階:社会的欲求 社会的役割を得たい、受け入れられたいという欲求
第四段階:承認欲求 評価されたいという欲求
第五段階:自己実現欲求 自分らしく生きたいという欲求
人間の欲求にはこれらの五段階があり、第一段階~第五段階へと順に満たされていくというものです。生理的欲求が満たされると、安全な暮らしがしたいという欲求がでてくる、といった感じです。人間は自己実現に向かって絶えず成長する、という仮説に基づいて作られた理論です。社会的役割がなかったり、孤立感がある状態で、いきなり自分らしく生きたいというモチベーションが沸いてもこないというのは納得できると思います。
2.感情
怒り、喜びといった情動や、憂鬱といった気分が、やる気を左右しています。
3.認知
行動や結果に、どのような意味や意義があるといった意識や信念のことです。
4.環境
人的環境(上司や教師や同僚など)、非人的環境(報酬など)、物的環境(部屋の明るさ、机などの配置など)もやる気に影響を及ぼします。
これら4つの要素が複雑に絡まって、その人のやる気を決めているのです。つまり、やる気をコントロールするということは、大変複雑で難しいことなのです。しかし、その一方で、やる気を理論的にアプローチすることで、コントロールする方法を見つけ出すこともできるかもしれません。
参考文献:モティベーションを学ぶ12の理論 鹿毛雅治編 金剛出版
関連するコラム
- ミネラルを知る~総論編~ 2021-04-12
- 炭水化物の適切な摂取量が明らかに?! 2020-01-21
- ミネラルを知る~各論編2~ 2021-05-07
- ミネラルを知る~各論編1~ 2021-04-23
- 食事における「たんぱく質」の役割~②なぜ、たんぱく質が大切なのか~ 2021-06-04
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
松田友和プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。